すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
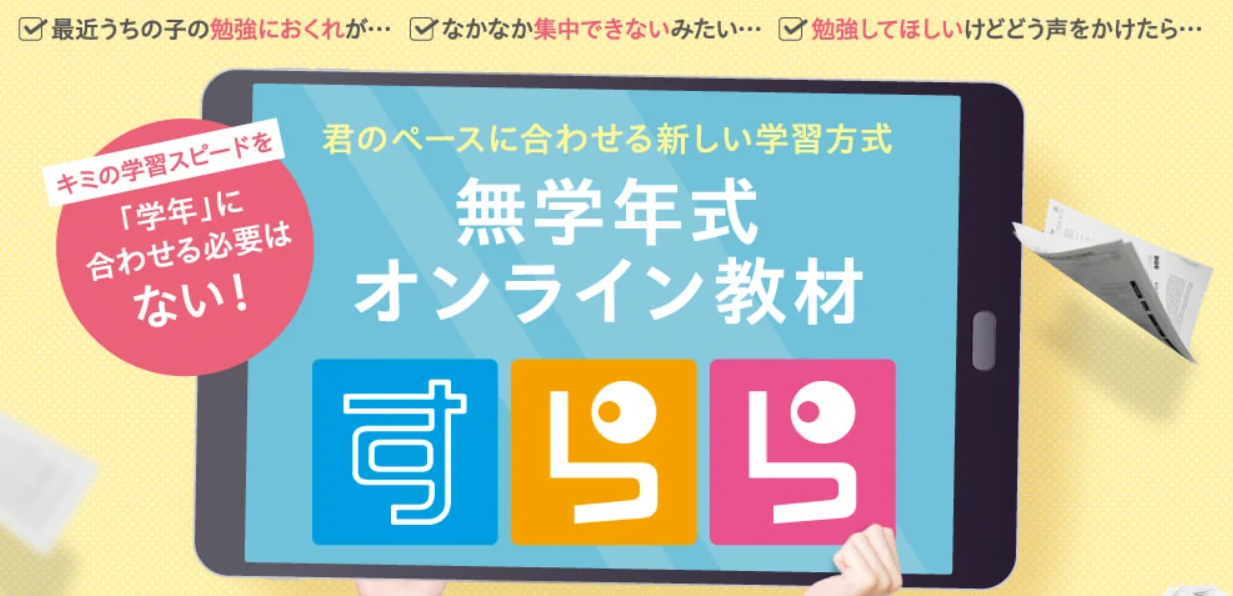
すららは、自宅で学習を続けることができるオンライン教材として、多くの不登校の子供たちに利用されています。
近年、文部科学省の「ICTを活用した学習活動の出席扱い制度」により、オンライン学習の実績が学校の出席として認められるケースが増えています。
すららもこの制度の対象となる学習ツールの一つであり、学校側に学習の進捗を証明できれば、出席扱いとなる可能性があります。
しかし、出席扱いとなるかどうかは学校や教育委員会の判断によるため、事前に相談することが大切です。
ここでは、すららが出席扱いになりやすい理由について詳しく解説します。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、単なるオンライン教材ではなく、学習の進捗を客観的に記録し、学習の質を証明できるシステムが整っています。
不登校の子供が出席扱いとなるためには、「自宅で適切な学習が行われていること」を示す必要がありますが、すららはその要件を満たすための仕組みが充実しています。
学習状況がデータとして自動記録され、学校側に提出できるレポートを作成できるため、家庭での学習が客観的に証明しやすいのが特徴です。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、子供の学習履歴が自動的に記録され、進捗状況が一目でわかるレポートを作成することができます。
このレポートには、学習時間や進んだ単元、理解度などの情報が含まれており、学校側に「どのような学習をどれくらい進めているのか」を具体的に伝えることができます。
出席扱いの判断基準の一つに「学習の記録が残っていること」があるため、すららのレポートは学校側にとっても有力な証拠となります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
すららの学習記録は自動的に保存されるため、保護者が手動で学習記録を管理する必要がありません。
多くの家庭では、子供が自宅学習をしていることを証明するために、手書きの学習日誌や進捗表を作成する必要がありますが、すららではこれらの手間が省けます。
さらに、データとして残ることで、学校側も「実際に学習が行われている」と客観的に判断しやすく、出席扱いの承認を得やすくなります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
不登校の子供が出席扱いとなるためには、「継続的に学習を行っていること」も重要な要素になります。
すららでは、専任のコーチが学習の計画を立て、継続的に学習を支援する体制が整っているため、計画性と継続性の両方を学校側に示すことができます。
単に「家で勉強しています」と伝えるだけでなく、「この計画で学習を進めており、定期的に進捗を確認しながら学んでいます」とアピールできるため、出席扱いの認定を受けやすくなります。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららには、学習をサポートする「すららコーチ」がついており、個々の子供に合った学習計画を提案してくれます。
学校側が出席扱いを認める際には、「計画的に学習が進められているか」「継続的に学習できているか」が重要なポイントになります。
すららのコーチング制度を活用することで、これらの要件を満たしていることを学校側に伝えやすくなり、出席扱いの承認を得やすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
すららのコーチは、子供一人ひとりの学習状況を把握し、学習計画を作成するだけでなく、学習の進捗を定期的にチェックしながらサポートしてくれます。
「今日はどこまで学習したのか」「どの単元でつまずいているのか」を確認しながら、学習の調整を行うため、計画通りに学習を進めることが可能です。
このような継続的なサポートがあることで、学校側も「しっかりとした学習計画に基づいて自宅学習が行われている」と認識しやすくなります。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
不登校の子供にとって、「学習の遅れ」は大きな不安要素の一つです。
すららは無学年式の学習システムを採用しており、学年にとらわれず、自分のペースで学習を進めることができます。
たとえば、算数は得意だから中学レベルの学習を進めたいけれど、国語は苦手だから小学校低学年レベルからやり直したい、といった調整が可能です。
こうした柔軟な学習スタイルは、学校側にも「子供が確実に学びを継続している」ことを示しやすく、出席扱いとして認められる可能性を高めます。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららが不登校でも出席扱いとして認められる大きな理由の一つに、家庭・学校・すららの三者がスムーズに連携できる仕組みが整っていることがあります。
出席扱いの認定には、学校が「自宅で適切な学習が行われている」と判断することが不可欠ですが、すららはそのためのサポートを積極的に行っています。
学習記録の提出や、学校とのやり取りをサポートすることで、保護者が一人で手続きを進める負担を軽減し、スムーズに出席扱いの申請を進められる環境を整えています。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いを申請する際、学校側に提出する必要書類が求められることがあります。
しかし、どのような書類を準備すればよいのか分からないという保護者も少なくありません。
すららでは、出席扱いの申請に必要な書類や、その準備方法について詳しく案内してくれるため、手続きをスムーズに進めることができます。
学校ごとに求められる書類の内容が異なる場合もあるため、個別の状況に応じたサポートが受けられるのも安心できるポイントです。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
学校に対して学習の進捗を証明するためには、学習レポートの提出が求められることがあります。
すららでは、専任コーチが学習レポートの作成をサポートし、必要に応じてフォーマットの準備や記入のアドバイスをしてくれます。
これにより、学校側に「どの科目をどの程度学習しているか」を明確に伝えることができ、出席扱いとして認められやすくなります。
特に、学習の継続性や達成度を示すデータがしっかりと整理されていることが、学校側の判断を後押しする要素になります。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
不登校の子供の出席扱いを申請する際には、学校の担任や校長と連絡を取る必要があります。
しかし、「どのように相談すればよいのか分からない」「学校にどう説明すればいいのか不安」という保護者も多いです。
すららでは、学校側とのコミュニケーションをスムーズにするためのアドバイスやサポートを提供しており、出席扱いの申請を円滑に進められるよう支援してくれます。
このように、学校との連携をサポートする体制が整っていることも、すららが出席扱いとして認められやすい理由の一つです。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省が推奨する「ICTを活用した学習支援」の一環として、多くの自治体や学校で導入されています。
近年、オンライン学習の活用が広がり、不登校の子供たちが自宅で学習を進めながら学校の出席扱いを認められるケースが増えています。
すららは、すでに全国の教育機関との連携実績があり、公式に「不登校支援教材」として利用されているため、学校側も導入のハードルが低く、出席扱いとして認めやすくなっています。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国の教育委員会や学校と協力し、不登校の子供たちの学習支援を行ってきた実績があります。
すでに導入している自治体や学校も多く、その実績があることで、学校側が「すららの学習を出席扱いとして認める」という前例を参考にしやすくなります。
不登校支援の経験が豊富なすららだからこそ、学校との調整がしやすく、出席扱いとしての認定を受けるためのサポート体制も整っています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文部科学省が推奨する「不登校の子供への学習支援ツール」として活用されています。
公式に不登校支援の教材として認められていることから、多くの学校が導入しやすくなっています。
また、すららを活用した学習が学校の教育課程に沿っているため、「学習の質が保証されている」と判断されやすく、出席扱いの認定を受けやすい環境が整っています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いとなるためには、学習環境が「学校の教育課程に準ずるもの」であることが求められます。
すららは、学習指導要領に沿った教材を使用しており、学習の評価やフィードバックの仕組みも整っているため、「学校に準ずる学習環境」として認められやすいのが特徴です。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの教材は、文部科学省の学習指導要領に準拠しているため、学校の授業と同じレベルの学習を進めることができます。
これにより、「学校に行かずに学習しているが、学校の教育課程に沿った学習を継続している」という証明がしやすくなり、出席扱いとして認められる要因の一つとなります。
学校側にとっても、「独自の教材で学んでいるのではなく、公的に認められた学習内容である」と判断しやすくなります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、学習の進捗状況を記録するだけでなく、理解度をチェックするテスト機能や、コーチによるフィードバックが受けられるシステムが整っています。
これにより、単に「学習した」という証明だけでなく、「どれくらいの学力が身についているのか」という点も明確にすることができます。
このような評価機能があることで、学校側も「学習の成果が確認できる」と判断しやすくなり、出席扱いとして認められる可能性が高まります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
不登校の子供が出席扱いになるためには、適切な手続きを踏んで学校側に申請する必要があります。
文部科学省の方針では、一定の条件を満たせばオンライン学習が出席扱いとして認められることがありますが、そのためには学校との連携が不可欠です。
すららを活用することで、学習の記録や進捗を証明しやすくなりますが、申請方法をしっかりと理解し、必要な準備を整えることが大切です。
ここでは、出席扱いの制度を申請する際の具体的な方法について説明します。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いの申請を進めるためには、まず学校側と相談し、必要な手続きを確認することが重要です。
学校によって出席扱いを認める条件が異なるため、担任の先生や校長、教育委員会と連携を取りながら進めていくことが大切です。
いきなり申請を進めるのではなく、まずは「出席扱いが可能かどうか」「どのような書類が必要か」について確認することで、スムーズに手続きを進めることができます。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いの申請には、学校側が求める書類を揃える必要があります。
一般的に、オンライン学習の利用を証明するための学習記録、学習計画、そして場合によっては医師の診断書が求められることがあります。
すららを活用する場合、学習の進捗レポートを学校に提出することで、継続的に学習していることを証明しやすくなります。
事前に学校側としっかり話し合い、どのような書類が必要なのかを明確にしておくことが大切です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
出席扱いの申請において、子供の不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書が求められるケースがあります。
特に、精神的な理由や発達障害などが関係している場合、医師の意見書が「学習の継続が望ましい」という証拠として有効になります。
すべてのケースで必須ではありませんが、学校側が申請を受理しやすくするために、診断書の準備を検討することも重要です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
不登校の理由はさまざまですが、特に「適応障害」「うつ」「発達障害による学校生活の困難」などが理由である場合、学校側が出席扱いを認める際に医師の診断書を求めることがあります。
これは、子供が単なる「さぼり」ではなく、正当な理由で学校に通えない状況であることを示すためです。
学校ごとに対応が異なるため、担任や校長と相談し、診断書が必要かどうかを確認することが大切です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
医師の診断書や意見書を取得する場合、精神科・心療内科・小児科などの専門医に相談することが一般的です。
診断書には、不登校の原因や現在の状態、そして「自宅での学習が継続されることが望ましい」といった内容を記載してもらうことが重要です。
すららを活用している場合は、「オンライン学習を活用し、一定の学習を継続している」という事実を医師に伝えることで、より具体的な内容の診断書を作成してもらいやすくなります。
診断書があることで、学校側も正式な証拠として判断しやすくなり、出席扱いの申請がスムーズに進みやすくなります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いの申請を進めるうえで、学習の進捗状況を示す記録が必要になります。
すららでは、学習履歴を自動的に記録し、レポートとして出力することができるため、学校側に提出することで「継続的に学習している」という証拠として活用できます。
この学習記録をもとに、学校側が出席扱いを判断しやすくなるため、申請手続きの重要なステップとなります。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららでは、学習時間・進捗・達成度などを記録したレポートをダウンロードすることができます。
このレポートを印刷またはデータとして保存し、担任や校長先生に提出することで、学習の継続状況を客観的に証明することができます。
学校側が出席扱いの判断を行う際に、具体的な証拠として役立つため、必ず用意して提出するようにしましょう。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
学校によっては、出席扱いの申請には正式な「出席扱い申請書」の提出が求められることがあります。
この申請書は、学校側がフォーマットを用意している場合もあれば、保護者が一緒に作成をサポートする場合もあります。
申請書には、学習の方法や使用教材、学習の継続状況などを記載し、学校側が出席扱いを判断しやすいようにまとめることが重要です。
すららの学習記録を活用することで、申請書の内容を具体的に説明しやすくなります。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いの最終的な判断は、学校や教育委員会が行います。
すららを活用して学習を続けていることが証明され、学校側が適切と判断すれば、出席扱いとして認められる可能性が高くなります。
学校によっては、校長先生の判断だけで出席扱いが決まる場合と、教育委員会の承認が必要な場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
多くの学校では、出席扱いの最終判断を校長先生が行います。
学校側に必要な書類を提出し、校長先生が「オンライン学習を活用した適切な学習が行われている」と判断すれば、出席扱いとして認められることになります。
出席扱いの基準は学校ごとに異なるため、事前にしっかりと相談し、必要な書類を揃えておくことが大切です。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
一部の自治体では、学校だけでなく、教育委員会の承認が必要な場合があります。
この場合、学校側が教育委員会に申請を行い、最終的な判断が下されることになります。
保護者は学校側と連携を取りながら、必要な手続きを進めることが重要です。
すららの学習記録や、学校が求める書類を揃えることで、スムーズに申請を進めることができます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校の子供にとって、学校に通えないことが学業や進路にどのような影響を与えるのか、不安に感じることは少なくありません。
しかし、文部科学省の方針により、オンライン学習を活用することで出席扱いになるケースが増えてきています。
すららは、学習の継続をサポートしながら、出席日数として認めてもらえる可能性がある教材の一つです。
出席扱いとして認められることで、内申点への影響を抑えたり、学習の遅れによる不安を軽減したりすることができます。
また、親の負担を減らし、家庭・学校・すららが連携して子供の学習を支える体制を整えることも可能です。
ここでは、すららを活用し、出席扱いとして認めてもらうメリットについて詳しく紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
不登校の状態が続くと、出席日数の不足によって内申点が大きく影響を受けることがあります。
特に中学・高校の進学を考えたときに、出席日数が足りないことが進路の選択肢を狭めてしまう要因となることがあります。
しかし、すららを活用して出席扱いとして認められれば、学習の継続が評価され、内申点の大幅な低下を防ぐことができます。
出席日数が確保されることで、学校側も学習意欲を持っていることを評価しやすくなり、進学や将来の選択肢が広がります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
内申点は、出席日数や授業への取り組み姿勢をもとに評価されることが多いです。
不登校が長期化すると、出席日数の不足が直接的に影響し、内申点が低くなってしまうケースがあります。
しかし、すららを利用して出席扱いが認められれば、「学校に通えなくても学習を続けている」という証明になり、内申点の評価が悪化するのを防ぐことができます。
学校側も「学習の継続性」を重視するため、すららの学習履歴をしっかり提出することで、評価を維持しやすくなります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席日数が確保できることで、進学時の選択肢が広がるというメリットもあります。
特に公立高校の入試では、内申点が合否に影響を与えるため、出席扱いとして認められることで、進学の可能性を高めることができます。
また、不登校経験があっても、すららを活用して学習を続けていた実績があれば、面接や推薦入試の際に「学習意欲がある」と評価されることにつながります。
出席日数を確保しながら学習を続けることで、将来の進路の選択肢を広げることができるのです。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校の子供は、「授業に遅れてしまったらどうしよう」「もう取り戻せないのではないか」といった不安を抱えやすいです。
しかし、すららは無学年式のカリキュラムを採用しており、どの学年の内容からでも学習をスタートできるため、自分のペースで学び直すことができます。
学校の授業に遅れを感じても、すららを活用すれば、焦ることなく学習を継続することができます。
このように、継続的な学習環境が整うことで、子供の自己肯定感の低下を防ぐことにもつながります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららは、学年に関係なく自分の理解度に合わせて学習を進められる「無学年式」システムを採用しています。
そのため、「授業に追いつけない」というプレッシャーを感じることなく、今の自分に合ったレベルから学び直すことができます。
また、すららコーチが学習計画をサポートしてくれるため、「どこから勉強すればいいのか分からない」といった不安を感じることなく、学習を継続することができます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
不登校の子供は、「自分は勉強についていけない」「もう遅い」といった気持ちになりやすく、自己肯定感が低下しがちです。
しかし、すららのようなオンライン教材を活用することで、家庭でも学習環境を整えることができ、「学習を続けられている」という実感を持つことができます。
学習を継続することで、「自分もできる」という自信につながり、将来的な学びへの意欲を高めることができます。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子供を支える親にとって、「勉強をどうすればいいのか」「このままでいいのか」といった悩みは尽きません。
しかし、すららを活用することで、家庭だけでなく、学校やすららコーチと協力しながら子供の学習を支えることができるため、親の負担を軽減することができます。
親だけが不安を抱えるのではなく、学校や第三者のサポートを受けながら学習環境を整えることで、より安心して子供の成長を見守ることができます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららでは、専任のコーチが学習計画を立てたり、進捗をサポートしたりするため、親がすべてを管理する必要がありません。
また、学校とも連携しながら学習の進捗を共有できるため、「このままで大丈夫だろうか」といった不安を軽減することができます。
親が一人で悩むのではなく、学校やすららのサポートを活用しながら、子供の学習を支える環境を整えることが大切です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
不登校の子供が「出席扱い」として認められることは、進学や学習の継続のためにとても大切です。
文部科学省のガイドラインに基づき、オンライン学習を活用することで出席日数としてカウントされるケースが増えていますが、そのためにはいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
学校側の理解を得ること、必要な書類を揃えること、医師の診断書が求められるケースがあることなど、事前に準備しておくべき点がいくつかあります。
ここでは、すららを活用して出席扱いを認めてもらう際の注意点について詳しく紹介します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを認めてもらうためには、学校側の理解を得ることがとても重要です。
すららを活用した学習が出席扱いとして認められるかどうかは、最終的に校長先生の判断によります。
そのため、担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生とも早めに相談し、すららが文部科学省のガイドラインに基づいた学習教材であることをしっかり説明することが大切です。
また、学校によってはオンライン学習の活用についての認識が異なるため、資料を準備し、具体的な学習内容を示しながら話を進めるとスムーズです。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省が認める「ICTを活用した学習支援」の一環として、多くの学校で活用されています。
しかし、すべての学校がすららのシステムについて詳しく理解しているわけではないため、「なぜすららで学習すると出席扱いになるのか?」を丁寧に説明する必要があります。
特に、文部科学省のガイドラインに基づいており、出席扱いとして認められる可能性があることをしっかり伝えることが大切です。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
すららの公式サイトやパンフレットには、出席扱いについての情報が掲載されているため、これらの資料を持参して学校側に説明すると理解が得やすくなります。
また、担任の先生だけではなく、最終的に判断を行う校長先生や教頭先生にも早めに相談し、学校全体での認識を統一してもらうことが重要です。
特に、学校ごとに出席扱いの基準が異なる場合があるため、早い段階で相談を進め、学校側と連携を取ることがポイントになります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の原因によっては、学校側が出席扱いを認めるために医師の診断書や意見書の提出を求めることがあります。
特に、「体調不良」や「精神的な理由」での不登校の場合、家庭学習を続けることが適切であるという証明が求められるケースが多いです。
そのため、事前に医師に相談し、出席扱いのための診断書を発行してもらう準備をしておくとスムーズに手続きを進めることができます。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
学校側が出席扱いを判断する際、不登校の理由が学業への影響を与えるものであるかどうかがポイントになります。
例えば、長期的な体調不良や、学校に通うこと自体が強いストレスになっている場合、医師の診断書があれば「無理に登校するのではなく、家庭学習を継続することが望ましい」と証明することができます。
診断書の有無によって、学校側の対応が変わることもあるため、必要に応じて早めに準備することが大切です。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を取得するには、かかりつけの小児科や心療内科を受診し、医師に「出席扱いの申請に必要な診断書を発行してほしい」と相談する必要があります。
すでに定期的に受診している場合は、これまでの経過をもとに診断書を書いてもらいやすくなります。
初めて診断書を依頼する場合は、「家庭で学習を継続していること」「すららを活用していること」などを具体的に説明すると、医師も適切な内容で診断書を作成しやすくなります。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書の内容は、学校側が出席扱いを判断する重要な資料となります。
そのため、単に「不登校の状態である」と記載されるだけでなく、「家庭学習を継続することで学習意欲が保たれている」「無理に登校するのではなく、家庭学習の環境を整えることが望ましい」といった前向きな内容が含まれていると、学校側も出席扱いとして認めやすくなります。
診断書を依頼する際は、家庭での学習状況や子供の学習意欲をしっかり医師に伝え、適切な内容で作成してもらうことが大切です。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、「学校の授業に準じた学習を行っている」と学校側に理解してもらう必要があります。
単に家庭で好きな勉強をするだけでは、学校の教育課程と見なされず、出席扱いにならない可能性があるため注意が必要です。
学習時間や学習内容を、学校の授業に近い形で整えることで、学校側に認められやすくなります。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
すららでの学習が「出席扱い」として認められるには、学習内容が学校のカリキュラムと一致していることが求められます。
たとえば、単にドリルを解いたり、好きな教科だけを学んだりするだけでは「自己学習」とみなされ、出席扱いにはならない可能性があります。
そのため、学校の授業内容と照らし合わせながら、必要な単元を学習し、記録として残しておくことが大切です。
すららは文部科学省の学習指導要領に準拠しているため、カリキュラムに沿った学習ができる点が大きな強みです。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いを認めてもらうためには、学習時間の確保も重要なポイントになります。
学校の授業時間に近い学習時間を確保することで、学校側も「継続的に学習が行われている」と判断しやすくなります。
目安としては、1日2〜3時間程度の学習時間を確保するのが望ましいとされています。
すららの学習記録を活用し、どのくらい学習したのかを証明できるようにしておくと、よりスムーズに申請が進みます。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
学習内容は、国語・数学(算数)・理科・社会・英語などの主要教科をバランスよく学習することが推奨されます。
学校によっては、「主要教科だけではなく、副教科(音楽・美術・体育など)も含めた学習が必要」と判断する場合もあるため、事前に学校側と相談しながら進めることが大切です。
すららでは、主要教科の学習が可能なため、バランスよく学習計画を立て、学校側に提出できる形に整えておくと良いでしょう。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いとして認めてもらうためには、学校との継続的な連携が欠かせません。
ただ学習を進めるだけではなく、「どのような学習を行っているのか」「進捗状況はどうか」といった情報を学校側と共有することで、学校側も安心して出席扱いを判断しやすくなります。
学校ごとに報告の頻度やフォーマットが異なるため、事前に担任の先生と相談しておくと良いでしょう。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学校側が出席扱いを認めるかどうかは、「継続的に学習が行われているか」を確認できるかどうかがポイントになります。
そのため、家庭での学習状況を学校と定期的に共有し、学習が進んでいることを示す必要があります。
学習状況の報告方法は学校によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららでは、学習記録をレポートとしてダウンロードすることができます。
このレポートを活用し、月に1回程度、学校側に提出することで、学習の進捗状況を証明できます。
学校側も客観的なデータを確認できるため、出席扱いの判断がしやすくなります。
学校によっては、レポートを紙で提出する場合と、データで提出する場合があるため、どのような形式で提出するのが良いかを事前に相談しておきましょう。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、出席扱いを認めるために、定期的な家庭訪問や面談を求められる場合があります。
これは、学習環境や生活習慣が整っているかを確認するために行われるものです。
家庭訪問や面談では、すららでの学習状況を説明し、学習計画や進捗を共有することで、学校側の理解を得ることができます。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
学校とのやり取りは、メールや電話を活用してこまめに進めるのが良いでしょう。
特に、学習計画や進捗状況について定期的に報告することで、学校側の理解を得やすくなります。
また、困ったことがあれば早めに相談し、柔軟に対応できるようにしておくと、スムーズに出席扱いの手続きを進めることができます。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
自治体によっては、学校側だけでなく、教育委員会の承認が必要になる場合があります。
特に、公立校では、教育委員会の方針に基づいて出席扱いが判断されることもあるため、学校と連携しながら進めることが大切です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請が必要な場合、追加の資料を求められることがあります。
たとえば、「学習計画書」「学習進捗の報告書」「家庭での学習環境の説明書」などが必要になることもあるため、学校側と相談しながら準備を進めましょう。
また、教育委員会によって求められる書類が異なるため、事前にどのような資料が必要かを確認し、早めに準備を整えておくと安心です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、いくつかの成功ポイントがあります。
学校ごとに対応が異なるため、ただ学習を続けるだけではなく、学校側に「この学習方法が適切である」と納得してもらう工夫が必要です。
特に、前例を示したり、本人の意欲を伝えたりすることで、学校側が受け入れやすくなるケースが多いです。
ここでは、すららを利用して出席扱いを認めてもらうための具体的なポイントを紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校側が出席扱いを認めるかどうかを判断する際、「過去に同じようなケースがあったかどうか」を重視することがあります。
そのため、すららを活用して出席扱いとなった他の学校の事例を紹介することで、学校側の理解を得やすくなります。
「すでに他の学校でも出席扱いとして認められている」という実績を伝えることで、学校側が安心して判断しやすくなるため、積極的に前例を活用しましょう。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
学校によっては、「オンライン学習で本当に出席扱いにできるのか?」と疑問を持つこともあります。
そのため、すららを活用して出席扱いを認められた他の学校の事例を紹介すると、学校側の理解が深まり、承認されやすくなります。
実際に、すららを導入している学校や、教育委員会と連携している事例があるため、それを参考にして伝えると良いでしょう。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトでは、出席扱いに関する実績が紹介されています。
これをプリントアウトして持参し、学校側に具体的なデータを示すことで、説得力が増します。
「全国の○○校で出席扱いとして認められています」といった情報があると、学校側も「他の学校が認めているなら」と判断しやすくなるため、資料を活用することが重要です。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
学校側が出席扱いを判断する際、「学習意欲があるかどうか」を重視することが多いです。
そのため、本人の意欲を具体的に伝えることが大切です。
学習記録だけではなく、本人が書いた学習の感想や目標を提出したり、面談の際に本人が意欲を伝えたりすることで、学校側に「この子は本気で学習を続けようとしている」と感じてもらえます。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
学習の記録だけではなく、本人の言葉で「どんなことを学んでいるのか」「これからどのように勉強していきたいか」といった感想や目標を記入したものを学校側に提出すると、より説得力が増します。
特に、不登校の子供にとっては「自分の気持ちを伝えること」が大切なポイントになるため、簡単なメッセージでも良いので、自分の言葉で書いたものを準備すると良いでしょう。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校によっては、出席扱いの申請にあたって、本人との面談を行う場合があります。
この面談の場で、本人が「すららを使って学習を頑張っている」「今後も継続して学習を進めていきたい」と伝えることで、学校側の判断が前向きになりやすくなります。
親が説明するだけでなく、本人が直接意欲を伝えることができると、より効果的です。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いを認めてもらうためには、「学習が継続できること」が大前提となります。
そのため、無理なく続けられる学習計画を立てることが重要です。
最初から無理なスケジュールを立ててしまうと、途中で挫折してしまう可能性があるため、本人のペースに合わせた学習計画を作成し、無理なく続けられる環境を整えましょう。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
学習を継続することが最も大切なポイントになります。
たとえば、最初は1日30分から始め、徐々に学習時間を増やしていくなど、無理のないペースで進めることが重要です。
計画通りに進められるようになれば、学校側も「この子は学習を継続できる」と判断しやすくなり、出席扱いの承認を得る可能性が高まります。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららでは、専任の「すららコーチ」が学習計画をサポートしてくれます。
学習の進め方やペースについて悩んだときは、コーチに相談しながら、現実的なスケジュールを立てると良いでしょう。
学校側に提出する際にも、「すららコーチと相談しながら計画的に学習を進めています」と伝えることで、信頼度が増します。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららには、学習計画のサポートを行う「すららコーチ」がいます。
出席扱いの申請には、学習レポートの作成や進捗管理が必要になるため、コーチのサポートを最大限活用することで、スムーズに手続きを進めることができます。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららコーチは、学習進捗の管理だけでなく、学校側に提出するレポートの作成もサポートしてくれます。
たとえば、「どの教科をどのくらい学習したか」「どの単元を学習したか」といった詳細な記録を、学校側にわかりやすく伝えるためのレポート作成を手伝ってくれます。
これにより、保護者の負担を軽減しながら、出席扱いの申請をスムーズに進めることが可能になります。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららというアプリに関して、「うざい」という口コミを見かけたことがありますか?では、なぜ人々が「すららはうざい」と感じるのでしょうか?このような感情が起きる理由には、幾つかの要因が考えられます。
一つ目の要因は、利用者にとって過度な通知やメッセージが送られてくることです。
アプリからの連絡が過剰になると、ユーザーはストレスを感じる可能性があります。
コミュニケーションのバランスを大切にすることは、アプリ運営にとって重要です。
また、仕様が複雑で使いにくい場合も、ユーザーが「うざい」と感じる要因の一つと言えます。
ユーザーは使いやすさを重視し、スムーズな操作を望みます。
したがって、シンプルかつ効率的なデザインが求められます。
さらに、プライバシーに関する配慮が不十分な場合、ユーザーに不快感をもたらす可能性があります。
個人情報の適切な管理やセキュリティ対策は、ユーザーに安心感を与える重要な要素です。
したがって、アプリ運営側は利用者の声に耳を傾け、改善に努めることが肝要です。
ユーザーの利便性と満足度を向上させるために、運営チームの努力が不可欠であり、定期的なアップデートや改善が求められます。
ユーザーと共に成長し、満足度を高めるために、常に改善を心がけることが大切です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららの発達障害コースの料金プランについてお知らせいたします。
当施設では、発達障害をお持ちの方々が適切な支援を受けられるよう、複数のプランをご用意しております。
料金は、コースの内容や期間、お客様のニーズに合わせて柔軟に設定されております。
初回カウンセリングを含むプランや、定期的なセッションが組み込まれたプラン、さらには個別のプランもございます。
料金に関しましては、お問い合わせいただくか、ウェブサイトにて詳細をご確認いただければと存じます。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
近年、不登校の子供たちの増加が社会的な課題となっています。
そのような状況下で、オンライン学習プラットフォームの中でもすららのタブレット学習が注目されています。
不登校の子供たちにとって、学校に出席することが難しい状況下で、すららのタブレット学習は有効な選択肢となるでしょうか。
不登校の子供がすららのタブレット学習を利用した場合、それは正式な出席として扱われるのでしょうか。
この点を明らかにするために、いくつかの観点から考察してみましょう。
まず第一に、現行の教育制度において、不登校の子供がすららのタブレット学習を通じて学習を行った場合、それを正式な出席と認めるかどうかは、学校や教育委員会の方針に依存するでしょう。
通常、学校の出席管理は学校内での出席を基準にしていますが、近年の教育の多様化やテクノロジーの進化により、オンライン学習の出席も一定の扱いを受けることがあります。
次に、すららのタブレット学習がどのような教育内容を提供しているかも重要な要素です。
もし、すららの学習内容が学校教育のカリキュラムに準拠し、一定水準の学習成果が得られると認められる場合、学校側もそれを出席扱いとして認める可能性が高まるかもしれません。
最後に、保護者や子供自身の意向も考慮されるべき点です。
不登校の背景には様々な事情がありますので、子供がすららのタブレット学習を通じて学ぶことで、学習意欲が向上し、学校への復帰の一助となる可能性もあります。
保護者や子供が積極的にその取り組みを支援し、学校とも連携を図ることで、出席扱いの是非も再検討されるかもしれません。
以上の観点から、不登校の子供がすららのタブレット学習を利用した場合、出席扱いとなるかどうかは様々な要因に左右されることが分かります。
教育の多様化やテクノロジーの進化に伴い、従来の枠組みにとらわれず、柔軟な対応が求められる時代かもしれません。
学校や関係機関、保護者、そして子供自
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
スララのキャンペーンコードの使い方について、詳しくご説明いたします。
まず、すららをご利用いただいている皆様にとって、キャンペーンコードはさまざまな特典や割引を受ける絶好の機会を提供しております。
キャンペーンコードをご利用いただくことで、お得な価格でコースを受講したり、特別なサービスを受けることができます。
キャンペーンコードの利用方法は非常に簡単です。
まず、お申し込みの際に、指定された欄にキャンペーンコードを入力してください。
その後、指定された手続きを完了することで、割引や特典が自動的に適用されます。
キャンペーンコードは通常、申し込み手続きの最後の確認画面などに記載されていますので、入力にお間違いがないようにご注意ください。
また、キャンペーンコードには有効期限がございますので、ご利用の際には必ず期限をご確認いただくようお願い申し上げます。
期限を過ぎてしまうと、特典や割引を受けることができない場合がございますので、お見逃しなくご注意ください。
キャンペーンコードを上手に活用して、すららのさらなる学びへの一歩を踏み出していただければと存じます。
何かご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを利用しているユーザーの皆様、退会方法についての情報をお探しの方々に、きちんとした手続きを通じて円滑にアカウントを閉鎖する方法についてお伝えいたします。
退会手続きを開始する前に、お客様のプランや契約に関するすべての情報が整理されていることをお勧めします。
すららの退会は簡単で、オンライン上で手続きが行えます。
退会手続きを開始するには、まずすららの公式ウェブサイトにアクセスしてください。
ログインした後、アカウント設定メニューから「会員情報の変更」を選択します。
そこで「退会手続きをする」をクリックし、画面の指示に従って手続きを進めてください。
お客様のアカウント情報や理由を入力し、最終確認画面で手続きを完了してください。
退会手続きが完了すると、ご登録いただいたメールアドレスに確認のメールが送信されます。
このメールに記載されたリンクをクリックすることで、退会手続きが最終的に完了します。
すららをご利用いただく際に生じたご不明点やご質問がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでお問い合わせください。
退会に関する手続きは、お客様のプライバシーやセキュリティを保護するために重要です。
すららをご利用いただいた経験に感謝申し上げますと共に、今後のことを考えての退会手続きも覚悟していただきたいと思います。
退会後も、大切な情報の閲覧や引き続きのサポートが必要な場合は、遠慮なくお知らせください。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららをご検討いただきありがとうございます。
入会金と毎月の受講料以外にかかる追加料金についてお尋ねいただきありがとうございます。
お答えしますと、通常、入会金と受講料以外に追加料金はかかりません。
すららでは、他の追加の費用や隠れたコストは一切ございませんので、ご安心ください。
受講料以外に必要なものが発生した場合には、事前に皆様にお知らせし、ご了承をいただいた上での実施となります。
すららをご利用いただく際には、費用についての透明性を大切にしておりますので、安心してお申込みください。
何かご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?この点に関しまして、一般的には1人の受講料を支払った場合、他の家族や兄弟が同じ教材やサービスを利用することは難しいケースが多いです。
一般的に、教育機関やサービスプロバイダーは、受講料を支払った個人にのみサービス提供を行うことが一般的です。
兄弟が一緒に受講する場合は、原則として別々の受講料が必要となることが一般的です。
このルールは、提供されるサービスや教材の質を維持し、教育機関やサービスプロバイダーが適切な運営を維持するために設けられています。
1人の受講料を支払うことで、その利用者に最適な教育環境やサポートを提供するため、個々の受講生に合わせたサービスを提供する必要があるためです。
そのため、兄弟間で一緒に利用したい場合には、事前に教育機関やサービスプロバイダーに相談し、適切な手続きや料金について確認することをお勧めします。
兄弟で一緒に受講するためには、追加の受講料が必要となる可能性が高いため、事前に慎重に条件を確認することが重要です。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには英語はありますか?というご質問にお答えいたします。
当社の小学生コースには、英語学習の機会がございます。
英語は、グローバルな言語として今後ますます重要性が高まることから、子供たちにとって非常に有益なスキルと言えます。
ですので、すららでは小学生の方々にも英語学習の機会を提供しております。
英語を学びたい・習得したいお子様にご満足いただけるよう、教材や指導方法にもこだわりを持っております。
皆さまのお子様が成長するお手伝いができれば幸いです。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららでは、専門家のコーチがあなたの学習をサポートします。
コーチは、個々のニーズや目標に合わせてカスタマイズされたレッスンプランを提供します。
また、定期的な進捗チェックやモチベーションを維持するための助言も行います。
コーチはあなたの成長を継続的にサポートし、問題や疑問があれば適切なアドバイスを提供します。
すららのコーチは、あなたの学習体験を充実させるために尽力します。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
今回は、不登校でも出席扱いになるすららについて、制度や申請手順、注意点についてまとめてきました。
すららを活用することで、不登校生徒が出席扱いとして学習を続けることが可能となります。
出席扱いになるためには、保護者が学校に届け出を提出し、教育委員会の認定を受ける必要があります。
また、定期的な進捗報告や指導計画の提出も欠かせません。
すららを活用する際には、注意点も押さえておく必要があります。
例えば、制度や手続きについて正確な情報を収集し、適切に申請手続きを行うことが重要です。
さらに、教育内容や進捗状況についてもきちんと把握し、学習の質を保つことが求められます。
また、不明点や問題が発生した際には、迅速に対応することも大切です。
すららを通じて不登校でも出席扱いになる制度を活用することで、生徒一人ひとりの学びや成長をサポートすることができます。
制度や手続きを理解し、適切に対応することで、生徒の学びの機会を確保し、学校生活における支援を充実させることができるでしょう。
不登校生徒の学びを支えるために、すららを活用する際には、制度や手順を遵守し、注意点をしっかりと押さえながら取り組んでいきましょう。

