すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
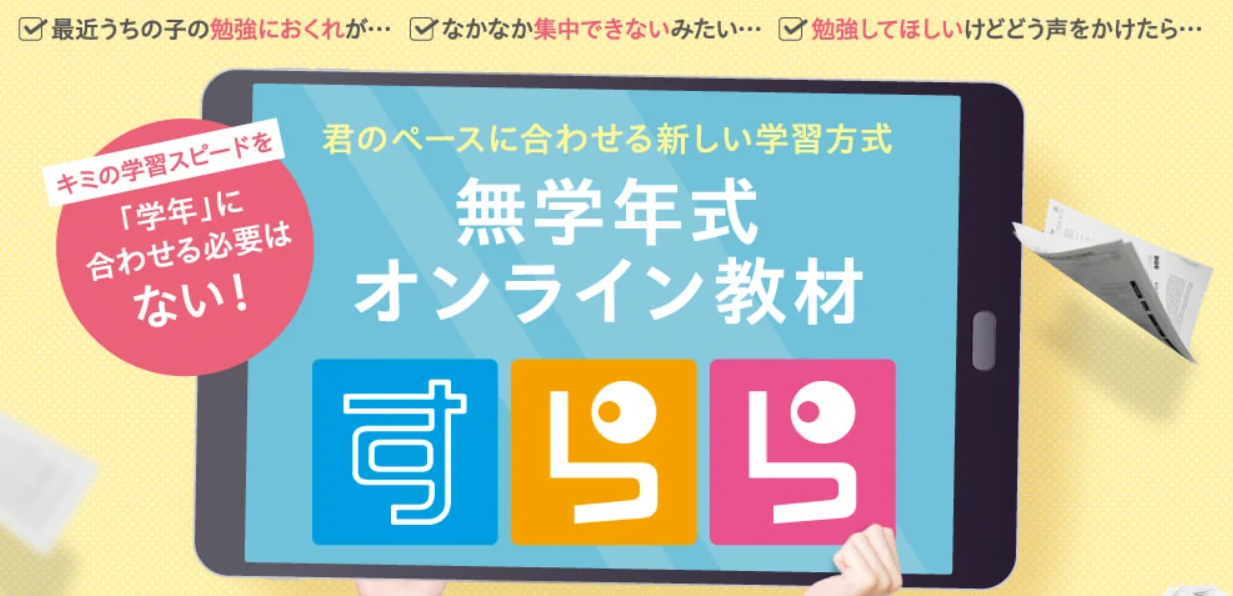
「すらら」というオンライン学習サービスについて、検索すると「うざい」というネガティブなワードを目にすることがあります。
しかし、実際にすららを利用している人たちの声を聞くと、メリットが多いこともわかります。
すららは、無学年式の学習システムや対話型授業など、他のオンライン学習とは異なる魅力を持っています。
この記事では、すららが選ばれる理由と、おすすめのポイントを詳しく紹介します。
すららが気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
すららのおすすめポイントをまとめました
すららは、従来の学習方法とは異なり、子どもの学力や特性に合わせた柔軟な学習が可能なサービスです。
特に「無学年式」の学習方法や、「すららコーチ」のサポート機能が人気のポイントになっています。
以下に、すららの主なおすすめポイントをまとめました。
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
すららの最大の特徴のひとつが、「無学年式」の学習スタイルです。
一般的な学校教育では、学年ごとに決められたカリキュラムがあるため、得意な科目があっても飛び級は難しく、苦手な分野があってもそのまま進んでしまうことが多いです。
しかし、すららでは学年の枠を超えて自由に学ぶことができるため、得意科目はどんどん先に進み、苦手な科目はさかのぼって復習できます。
これにより、子ども一人ひとりのペースに合わせた学習が可能になります。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
無学年式の学習のメリットは、子どもの学力や理解度に合わせて自由に学習を進められることです。
例えば、小学1年生でも英語が得意なら中学英語に挑戦できますし、中学2年生でも算数が苦手なら小学校の内容に戻って学ぶことができます。
これにより、「学校の授業についていけない」「簡単すぎてつまらない」といった悩みを解消できるのが魅力です。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
学校の授業では、クラス全員が同じペースで進むため、理解が追いつかなくても次に進んでしまうことがあります。
しかし、すららでは自分のペースで学習できるため、苦手な分野はしっかり復習し、得意な分野はどんどん先へ進むことができます。
例えば、算数の分数が苦手な場合は、小学校の基礎からやり直してしっかり理解することが可能です。
また、得意な子は学年を超えて先の内容に進めるため、学習のモチベーションを保ちやすいのも特徴です。
このように、すららの無学年式学習は、個々の学習ペースに合わせた柔軟な学びを実現し、効率的に学力を伸ばすことができるのが大きなメリットです。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
すららの大きな魅力の一つが、「対話型アニメーション授業」です。
一般的なオンライン学習教材では、テキストを読んだり、動画を見たりするだけのものが多いですが、すららはアニメーションを使って双方向のやりとりをしながら学習を進めることができます。
これにより、子どもが一方的に学ぶのではなく、実際に会話をしながら学べるため、飽きにくく、楽しく勉強を続けることができます。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
すららの授業では、アニメキャラクターが先生役となり、子どもと会話しながら学習を進めます。
質問に答えたり、ヒントを出したりすることで、子どもが考える力を養えるのが特徴です。
「授業を受ける」というよりも、「先生と話しながら学ぶ」という感覚に近いため、勉強に苦手意識がある子どもでも取り組みやすくなっています。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
すららの授業では、文章だけではなく、図やアニメーションの動きを使って解説が行われます。
特に、算数や理科などの「概念を理解するのが難しい科目」では、図や動きがあることでイメージしやすくなります。
例えば、「分数の計算」や「物理の法則」など、文字だけではわかりにくい内容も、アニメーションを見ながら学ぶことで直感的に理解しやすくなります。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
勉強を続けるためには、「褒められること」も重要です。
すららのアニメキャラクターは、子どもが問題を解くたびにリアクションをとってくれたり、励ましたりしてくれます。
特に、飽きっぽい子や、勉強に苦手意識を持っている子にとっては、こうした「褒められる体験」がモチベーションの維持につながります。
これにより、「やらされる勉強」ではなく、「自分から進んでやりたくなる勉強」に変わるのがすららの魅力です。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
オンライン学習を始めるときに親が気になるのは、「子どもがちゃんと続けられるか」「学習計画をどう立てるか」といった点です。
すららには「すららコーチ」という専属のサポーターがついているため、親が細かく管理しなくても学習を進めることができます。
仕事や家事で忙しい親にとっては、手間をかけずに学習のサポートをしてもらえるのは大きなメリットです。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
すららでは、子どもの学習状況に応じて「すららコーチ」が学習計画を作成し、進捗をフォローしてくれます。
これにより、子ども一人で学習するのではなく、適切なペースで学習を進められるように調整してもらえるため、「何をどのくらいやればいいのか分からない」と悩むことがなくなります。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
すららコーチは、子ども一人ひとりの特性や学習スタイルに合わせて、個別に学習計画を立ててくれます。
「得意な科目をもっと伸ばしたい」「苦手科目を重点的にやりたい」といった要望にも柔軟に対応してくれるため、それぞれの子どもに合った最適な学習プランを作成してもらえます。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
すららでは、子どもが学習中に分からないことがあった場合、すららコーチに直接質問や相談をすることができます。
これにより、親がつきっきりで勉強を教える必要がなく、子どもは自分のペースで学習を進めることができます。
親は基本的に見守るだけでいいので、「勉強を教えるのが苦手」「忙しくて時間が取れない」という方でも安心して利用できます。
このように、すららは「対話型アニメーション授業」で楽しく学べるだけでなく、「すららコーチ」のサポートによって、子どもが自主的に学習できる環境が整っています。
親の負担を減らしながら、子どもが自分で勉強する習慣を身につけられるのが、すららの大きな魅力です。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららは、発達障害のある子どもや、不登校で学校の授業についていくのが難しい子どもにも対応したオンライン学習サービスです。
一般的な学習教材では、決まったペースで進める必要がありますが、すららは「無学年式」で自由に学習できるため、一人ひとりに合った方法で学ぶことができます。
また、つまずきをAIが分析し、自動で適切な問題を出題してくれるため、無理なく学習を続けることができます。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららは、その優れた学習支援機能が評価され、文部科学大臣賞を受賞しています。
この賞は、教育分野で特に優れた取り組みに贈られるもので、すららが「子ども一人ひとりの学習をサポートするツール」として高く評価されている証拠です。
単なるオンライン学習教材ではなく、発達障害や不登校など、さまざまな学習の悩みを抱える子どもたちの支援を目的としたツールとして、多くの家庭や教育機関で活用されています。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
発達障害を持つ子どもにとって、学校の授業についていくのは簡単なことではありません。
しかし、すららは「無学年式」で学習できるため、わからない部分を何度も繰り返したり、自分のペースでじっくり学んだりすることが可能です。
また、アニメーションを活用した対話型の授業なので、文字だけの教材よりも理解しやすく、集中しやすい設計になっています。
これにより、ADHDや学習障害のある子どもでも安心して取り組むことができます。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
不登校の子どもにとって、学校の授業に戻ることは大きなハードルになります。
「授業の内容がわからない」「どこから復習すればいいかわからない」という悩みを持つことも少なくありません。
しかし、すららなら、学年に関係なく学べるため、学校の授業に追いつくための復習がしやすくなっています。
さらに、家で自分のペースで学べるため、焦らずに少しずつ学習を進めることができます。
つまずきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
すららにはAI機能が搭載されており、子どもがどこでつまずいているのかを自動で解析してくれます。
そして、理解が不十分な部分に関連する問題を自動的に出題し、繰り返し学習できるようになっています。
「どこがわからないのかがわからない」という状況を防ぎ、確実に苦手を克服できるのが大きなポイントです。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
学習を続ける上で大切なのは、「どれだけ成長できたか」をしっかり確認できることです。
すららでは、オンラインテストやリアルタイム学力分析機能を活用することで、学習の成果を可視化できます。
これにより、子ども自身の達成感を得られるだけでなく、保護者も学習の進捗を把握しやすくなります。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
すららには、学習後すぐに理解度を確認できる小テストが用意されています。
テストの結果はその場でフィードバックされ、間違えた問題については解説が表示されるため、すぐに復習することができます。
「間違えたまま放置してしまう」ということがなく、その場で理解を深められる仕組みになっています。
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
学習を進めていると、自分では「できたつもり」になっていても、実際には理解が不十分な場合があります。
すららの定着度診断では、AIが子どもの学習状況を分析し、苦手な分野を特定してくれます。
その結果をもとに、苦手克服のための対策問題が自動的に出題されるため、効率よく学習を進めることができます。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
オンライン学習では、「子どもが本当に勉強しているのか」「どれくらい理解しているのか」が見えにくいと感じる保護者の方も多いかもしれません。
しかし、すららでは、学習の進捗や理解度を示すレポートが保護者にも配信されるため、子どもがどれくらい学習を進めているのかを把握することができます。
これにより、「ちゃんと勉強しているのか心配…」といった不安を解消できるのも、すららの大きな魅力のひとつです。
このように、すららは発達障害や不登校の子どもにも対応した学習ツールとして、多くの家庭で活用されています。
また、学習成果をしっかり可視化できる仕組みも整っているため、安心して利用することができます。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
すららでは、英語の学習が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3つの技能に対応しています。
これにより、英語のスキルをバランスよく伸ばすことができるため、英語力を総合的に高めたいと考えている子どもに最適な教材となっています。
それぞれの技能をしっかり学べる機能が充実しており、英検やTOEICなど、さまざまな英語の試験対策にもおすすめです。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
リスニング力を向上させるためには、ネイティブスピーカーの音声を聞くことが重要です。
すららでは、ネイティブの音声で英語のリスニングを学ぶことができ、発音やイントネーションの正確さを自然に身につけることができます。
英会話に必要なリスニング力を養成するため、実際の会話に近い音声を使った学習ができるのが特徴です。
これにより、リスニング力が効率的に向上し、英語を実際に使う場面でも自信を持って対応できるようになります。
音読チェックでスピーキング練習ができる
英語を話す力を伸ばすためには、スピーキングの練習が欠かせません。
すららでは、音読チェックの機能があり、子どもが英語の文章を正しく発音できているかを確認することができます。
自分の発音がネイティブとどれくらい近いかをフィードバックしてくれるため、スピーキング力を効果的に向上させることができます。
これにより、英語を話す自信がつき、実際の会話でもスムーズに言葉が出るようになります。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
英語学習において、単語や文法の基礎をしっかり学ぶことは非常に重要です。
すららでは、英単語や文法の解説をアニメーションで行い、視覚的に理解を深めることができます。
難しい文法の概念や語彙も、アニメーションを使って分かりやすく説明してくれるので、英語の基礎を楽しく学べます。
これにより、英検の勉強やTOEIC、TOEFLなど、さまざまな試験の対策としても効果的です。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
すららの料金体系は、非常に柔軟でコストパフォーマンスが高い点が魅力です。
1つの契約で、複数の兄弟が同時に利用できるため、家族全員で使うことができます。
また、必要な科目だけを追加できるので、無駄なく学習を進めることができるのです。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
すららでは、1つの契約で複数の兄弟が同時に利用できるため、兄弟が多い家庭でもお得に利用できます。
例えば、兄が中学生で妹が小学生の場合でも、同じ契約内で学習を進めることができ、人数分の追加料金が発生することはありません。
このシステムは、家庭で複数の子どもがいる場合、非常にコストパフォーマンスが高く、家計にも優しい設計となっています。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
小学生の兄と中学生の妹がいる家庭でも、すららなら同じ契約内で学習を進められます。
それぞれの子どもに合わせたカリキュラムが提供されるため、学年や学習内容が異なっていても問題ありません。
このように、兄弟がいる家庭では非常にお得に利用できるため、家庭内での学習サポートの負担も軽減できます。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
すららの料金プランでは、必要な科目だけを選んで追加することができるため、無駄なく学習を進めることができます。
たとえば、算数や英語は重点的に学びたいけれど、他の科目は必要ないと感じる場合、無駄な科目の料金を払うことなく、自分に必要な学習だけを選択できます。
この柔軟性が、家計に優しいだけでなく、子どもの学習ニーズにもぴったりフィットします。
このように、すららは兄弟での利用も可能で、科目ごとに必要なものだけを選んで学べるため、非常にコスパが良い学習サービスです。
家庭ごとに適切なプランを選べる点が、すららの大きな魅力です。

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
すららは、家庭用のタブレット学習教材の中でも特に特徴的なサービスを提供しています。
しかし、「すららはうざい」という声が一部で聞かれることもあります。
それは、すららの学習スタイルが一般的な教材と異なっているため、誤解されている部分があるのかもしれません。
実際のところ、すららには他の家庭用タブレット教材にはない多くのメリットがあります。
ここでは、すららの魅力について詳しく解説していきます。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
オンライン学習教材の中には、映像授業や問題集が提供されるだけで、学習の進め方は子ども任せになってしまうものもあります。
そのため、「ちゃんと進められるのか」「勉強のペースを管理できるのか」といった不安を感じることもあるでしょう。
しかし、すららでは「すららコーチ」と呼ばれるプロの学習コーチがサポートしてくれるため、安心して学習を進めることができます。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
すららでは、専任の「すららコーチ」が子どもの学習の進捗を管理してくれます。
どの単元をどのくらい進めるべきかを把握し、適切なアドバイスをしてくれるため、子どもが一人で勉強を進めるのが苦手な場合でも、迷わず学習を続けることができます。
コーチが定期的にフォローしてくれることで、学習の習慣づけもしやすくなります。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
子どもによって得意・不得意な科目や、集中できる時間は異なります。
すららコーチは、それぞれの子どもの特性や生活リズムに合わせた学習スケジュールを作成してくれるため、無理なく学習を続けることができます。
たとえば、「苦手な算数を少しずつ進めたい」「英語は短時間で効率よく学びたい」といった要望にも柔軟に対応してくれるのが特徴です。
これにより、親が学習計画を管理しなくても、安心して学習を任せることができます。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
すららは、不登校や発達障害を持つ子どもたちにも対応した学習システムを提供しています。
学校に通うのが難しい子どもや、集団学習が苦手な子どもにとって、自宅で安心して学習を進められる環境を整えているのが大きなメリットです。
さらに、文部科学省の推薦教材としても採用されており、教育機関からの評価も高い学習ツールとなっています。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、文部科学省により推薦される学習教材として、全国の多くの学校や教育機関で採用されています。
特に、不登校の子どもや発達障害を持つ子ども向けに設計されており、通常の学習が難しい子どもでも、無理なく学べるように工夫されています。
この実績があることで、すららが信頼できる教材であることがわかります。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
不登校の子どもにとって、「授業に出席できないことで学習の遅れが心配」という問題があります。
しかし、すららを活用して学習を続けることで、学校によっては「出席扱い」として認められる場合があります。
これは、すららの学習内容が、学校のカリキュラムと連携しているためです。
出席日数の確保が必要な子どもにとって、大きなメリットとなります。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
すららは、発達障害を持つ子どもが学習しやすいように、特別なカリキュラムやサポートを提供しています。
たとえば、ADHDの子どもは集中力が続きにくい傾向がありますが、すららではアニメーションを使った視覚的な授業を取り入れることで、飽きずに学習できるようになっています。
また、学習の進め方を自由に調整できるため、理解が追いつかない場合でも、無理なく復習しながら学べるのが特徴です。
このように、すららは「すららコーチ」による対人サポートがあるだけでなく、不登校や発達障害を持つ子どもたちにも対応した学習ツールとして、多くの家庭や学校で活用されています。
自分のペースで学びたい子どもや、集団学習が苦手な子どもにとって、非常に心強い学習環境を提供してくれる教材といえるでしょう。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
すららの大きな特徴のひとつが「無学年学習」です。
一般的な学習教材では、学年ごとに学ぶ範囲が決められていますが、すららでは学年に縛られず、自分のペースで学習を進めることができます。
これにより、「得意な科目はどんどん先取り」「苦手な科目は基礎からじっくり復習」といった柔軟な学習が可能になります。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
すららの無学年学習は、小学生でも中学レベルの学習に挑戦できたり、中学生が小学校の範囲に戻って復習できたりするのが大きな魅力です。
例えば、「英語が得意な小学5年生が中学1年の英語を学ぶ」「算数が苦手な中学2年生が小学4年生の内容から復習する」といったことが自由にできます。
このように、子ども一人ひとりの理解度やペースに合わせた学習ができるため、無理なく確実に学力を伸ばすことが可能です。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達障害(ASD、ADHD、LDなど)を持つ子どもは、集団授業のペースについていくのが難しいことがあります。
特に、わからない部分を理解しないまま次の単元へ進んでしまうと、学習の遅れが積み重なり、自信を失ってしまうことも。
しかし、すららの無学年学習なら、自分が理解できるまでじっくり学ぶことができるため、焦らずに自分のペースで進めることができます。
学校の進度に関係なく、自分に合った学習方法を選べるのは、大きな安心材料となるでしょう。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららは、AIによる学習診断と、すららコーチによる対人サポートを組み合わせた「Wサポート」が特徴です。
ただAIが自動的に問題を出すだけでなく、人間のコーチが学習状況を確認し、必要に応じて調整を行うため、子どもにとって最適な学習プランを提供できます。
AIと人間のハイブリッドサポートにより、より精密な学習設計が可能になっています。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
他のオンライン学習サービスでは、AIによる自動出題機能があるものも増えていますが、すららはそれに加えて「すららコーチ」による対人サポートがある点が大きな違いです。
AIはデータ分析に基づいて効率的に学習を進められますが、一方で子どもが感じる学習のストレスやモチベーションの維持まではカバーしきれません。
すららでは、AIが学習状況を分析し、すららコーチがその結果をもとに細かいサポートを行うため、より個別最適化された学習が可能になります。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
AIは正確なデータ分析が得意ですが、「やる気がなくなってきた」「特定の単元でつまずいている」といった心理的な要因まで考慮することは難しい場合があります。
そこで、すららコーチが子どもの学習状況を見守りながら、必要に応じて学習スケジュールの見直しやアドバイスを行ってくれます。
「今日はこの単元をもう少し復習しよう」「ここまで頑張ったから少しペースを落とそう」といった微調整をしてくれるため、無理なく継続できるのがポイントです。
AIと人間のコーチングを組み合わせることで、より精密で効果的な学習設計ができるのが、すららの強みといえるでしょう。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
すららはタブレットやパソコンで完結するオンライン学習教材ですが、デジタル教材でありながら「記述力」を鍛えることができる点も大きな特徴です。
一般的なデジタル教材は選択式の問題が多く、「書く力」を養う機会が少なくなりがちですが、すららでは「論理的に考え、説明する力」を伸ばせるように工夫されています。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
すららの国語や作文のカリキュラムでは、単なる知識の暗記ではなく、「自分の考えを言葉にして説明する」力を重視しています。
例えば、文章を読んだ後に「この登場人物の気持ちを説明しなさい」「筆者の主張を自分の言葉でまとめなさい」といった問題が出題され、論理的な記述力を養うトレーニングができます。
これは、将来的に必要とされる「表現力」「論理的思考力」を鍛えるうえで非常に有効です。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
通常、記述力を鍛えるためには紙に書くトレーニングが必要とされますが、すららではタブレットやパソコン上で記述の練習ができるため、紙を使わずに「書く力」を養えます。
これは、デジタル教材の中では非常に珍しいポイントです。
紙のノートを使わずに、画面上で記述問題を解くことができるため、手軽に取り組めるのもメリットのひとつです。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
学習習慣が途切れてしまうと、再び学習を始めるのが難しく感じることがあります。
しかし、すららは「途中でやめても再開しやすい」仕組みが整っているため、一度中断してもスムーズに学習を再開できるのが大きな強みです。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
すららは、いつでも好きなタイミングで学習を始めたり、中断したりすることができるため、「しばらく休んでいたけど、また勉強を再開したい」というときにもスムーズに復帰できます。
学校の授業のように決まったスケジュールで進むのではなく、個別に学習を進めるスタイルなので、「前回どこまでやったか」がすぐに分かり、再開しやすいのが特徴です。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
不登校や発達障害を持つ子どもは、体調や気分の波によって「今日は勉強できるけど、明日は難しい」といった状況が起こりやすいものです。
すららは、そのような子どもの特性を考慮し、学習ペースを柔軟に調整できるようになっています。
「今日は調子がいいからたくさん進める」「疲れたら数日休んでまた再開する」といった学習スタイルが可能なので、プレッシャーを感じることなく続けられるのがポイントです。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、単なるオンライン学習教材ではなく、教育機関との連携実績が豊富な点も大きな魅力です。
特に、不登校の子どもにとっては「学校の授業を受けられないことで出席日数が足りなくなる」という問題がありますが、すららを利用することで「出席扱い」として認められるケースが増えています。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
すららは文部科学省のガイドラインに基づき、一定の条件を満たすことで「在宅学習でも出席扱い」として認められることがあります。
実際に、すららを導入している学校の中には、「すららで学習を進めていれば、学校に通えなくても出席として認める」といった制度を取り入れているところも多くあります。
これにより、不登校の子どもでも学習を続けながら、学校の単位を取得することが可能になります。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは、不登校支援の一環として、全国の教育委員会や学校、さらには病院とも連携して学習支援を行っています。
例えば、病気や精神的な理由で長期間通学が難しい子どもでも、すららを利用することで学習を継続し、将来的に学校復帰しやすい環境を作ることができます。
このように、単なる家庭学習用の教材にとどまらず、教育現場や支援機関と協力しながら子どもたちの学習をサポートしているのが、すららならではの特徴です。

【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
すららは多くのメリットがある一方で、「うざい」と感じる人もいるようです。
これは、すららの特徴や学習スタイルが合わないと感じる場合に出る意見だと考えられます。
どんな教材にも向き不向きがあるため、デメリットもしっかり理解したうえで利用を検討することが大切です。
ここでは、すららのデメリットや「うざい」と言われる原因について詳しく紹介します。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららの特徴のひとつに、「すららコーチによる学習サポート」があります。
これは、子どもの学習状況をチェックし、必要に応じてアドバイスやフォローを行ってくれるサービスですが、人によっては「連絡が多すぎる」と感じることもあるようです。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
すららコーチは、学習の進捗を確認しながら適切なアドバイスをしてくれますが、「あまり干渉されたくない」「自分のペースで勉強したい」という子どもには、サポートが逆にプレッシャーになることもあります。
また、「今日は気が乗らないから勉強を休みたい」という場合でも、コーチから進捗の確認やアドバイスの連絡が入ることがあり、それを負担に感じることがあるかもしれません。
そのため、「自分で学習を進めるのが得意」「誰かに管理されるのが苦手」という子には、すららのサポート体制が合わない可能性があります。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららは、AIによる学習計画の自動作成機能があり、効率よく学べるようにカリキュラムを提案してくれます。
しかし、この機能が逆に「決められた通りにやらなければならない」と感じてしまうことがあり、それがプレッシャーになってしまうケースもあります。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
すららのAIは、子どもの学習状況を分析し、最適な学習計画を作成してくれます。
しかし、「今日はこの単元をやるべき」「このペースで進めないといけない」といった指示が細かく設定されるため、自由に学びたい子どもにとっては「縛られている」と感じることもあるようです。
特に、「自分のペースで気分が乗ったときに学習を進めたい」「今日は別の科目を勉強したい」といった希望がある場合、AIの指示が負担に感じてしまうこともあります。
また、AIが提示する学習計画はあくまでデータに基づいたものであり、「その日の気分や体調を考慮してくれるわけではない」という点も注意が必要です。
計画通りに進められないと「遅れてしまった」と感じやすく、それがストレスにつながることもあるかもしれません。
そのため、学習に対する自主性を大切にしたい子どもには、すららの学習管理システムが合わない可能性があります。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららは、アニメーションを活用した「対話型授業」が特徴ですが、この演出が「子どもっぽい」と感じることもあります。
特に、小学校低学年の子どもには親しみやすく学びやすい仕組みになっていますが、高学年や中学生以上になると「キャラの会話がくどい」「もっとシンプルに学びたい」と感じる子もいるようです。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
すららの授業は、アニメキャラがナビゲートしながら進んでいきます。
これは、小さい子どもにとっては楽しく学べる工夫ですが、高学年や思春期の子どもには「幼稚に感じる」「もっと淡々と学びたい」と思われることもあります。
特に、普段から大人向けの学習コンテンツに慣れている子や、アニメに興味がない子にとっては、キャラクターの存在が「うざい」と感じられる原因になることもあるようです。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
すららは、オンラインでの無料体験や資料請求ができるため、一度申し込むとフォローの連絡が入ることがあります。
これは「親切なサポート」とも取れますが、頻繁に連絡が来ると「しつこい」と感じる人もいるようです。
特に、SNSでは「営業がうざい」「勧誘のメールが多い」といった声も見かけることがあります。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
すららの営業活動は、積極的なフォローアップが特徴です。
無料体験や資料請求をしたあとに、電話やメールでの案内が来ることがあり、これを「丁寧な対応」と感じる人もいれば、「勧誘がしつこい」と感じる人もいます。
SNSでは、特にこの「営業連絡の多さ」が気になるという声が上がることがあり、それが「うざい」と言われる原因の一つになっているようです。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららは、オンライン学習教材の中でも比較的料金が高めの部類に入ります。
すららコーチによるサポートや、AIを活用した学習システムが含まれているため、単なる映像授業と比べるとコストがかかるのは仕方がない部分ですが、実際に使ってみて「効果が感じられない」と思う家庭もあるようです。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
すららは「自宅での自主学習」を前提とした教材なので、子どもが積極的に取り組まないと学習効果を実感しにくい場合があります。
特に、親が「すららに任せておけば勉強するだろう」と思っていると、子どもが自分から学習しないまま時間だけが過ぎ、「結局、効果がなかった」と感じてしまうこともあるようです。
教材そのものの質は高いものの、学習習慣がついていない子どもには、親のサポートが必要になる場合もあります。
そのため、すららの料金を「高い」と感じるかどうかは、子どもの学習姿勢や家庭のサポート体制によっても変わってくるようです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
すららは、家庭で学べるオンライン学習教材の中でも、無学年学習やAIサポート、すららコーチの個別指導が受けられる点が特徴です。
ただし、「料金が高いのでは?」と気になる方もいるかもしれません。
ここでは、すららの料金プランについて詳しく解説していきます。
自分の家庭に合ったコースを選ぶ際の参考にしてください。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
すららを利用するには、最初に入学金がかかります。
コースによって異なるため、どのプランが自分に合っているのか確認してみましょう。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららでは、3教科(国語・数学・英語)を学べるコースが用意されています。
毎月払いと4ヵ月継続コースの2種類があり、長期間継続するほどお得になります。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
3教科に加えて理科・社会も学びたい場合、4教科コースが選べます。
こちらも、毎月払いと4ヵ月継続コースの2種類があります。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
5教科すべてを学びたい場合は、5教科コースが用意されています。
こちらは、小学生から高校生まで対応しており、総合的に学習を進めたい方におすすめです。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
すららの料金は、他のオンライン教材と比べるとやや高めに設定されていますが、その分、無学年学習やAIサポート、すららコーチによる個別指導など、充実した学習サポートが受けられます。
「タブレット学習だけでは続かない」「個別指導を受けながら自宅で学習を進めたい」という方には、コスト以上の価値を感じられるかもしれません。
どのコースが自分の学習スタイルに合っているか、しっかり比較検討してみることをおすすめします。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
すららは、家庭で学べるタブレット教材の中でも、無学年式学習やAIサポートが特徴的な学習システムです。
しかし、「本当に勉強効率がいいの?」「成績は上がるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、すららの勉強効果について、特に3教科コース(国語・数学・英語)を中心に詳しく紹介します。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
すららの3教科コースは、基礎学力を効率よく定着させることを目的としたカリキュラムになっています。
学校の授業についていけない子どもや、短期間で成績を向上させたい子どもにとって、大きなメリットがあります。
ここでは、すららの3教科コースを活用することで得られる具体的な勉強効果について見ていきましょう。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららは、アニメーションを使った対話型授業で、わかりやすく基礎を学べるのが特徴です。
特に、数学や英語のような積み重ねが必要な教科では、「わかったつもり」を防ぎながら、確実に基礎力を身につけられる仕組みになっています。
苦手な単元は何度も繰り返し学習できるため、学校の授業では理解しきれなかった部分も補強しやすいです。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
すららのカリキュラムは、「できる(基礎)→わかる(理解)→応用(実践)」の3ステップを重視しています。
例えば、数学ではまず簡単な計算問題を解いて基本を確認し、その後、アニメーションを活用した解説で概念を理解します。
最後に、応用問題を解くことで、「知識を使える力」に変えていくのが特徴です。
この流れがあることで、単なる暗記ではなく、実際に問題を解く力が身につきます。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生にとって、内申点に直結するのが国語・数学・英語の主要3教科です。
すららの3教科コースでは、定期テストで点数を上げるための対策も充実しています。
特に、AIが苦手分野を分析し、効率よく復習できる機能があるため、テスト前の勉強にも役立ちます。
「定期テストの点数を上げたい」「内申点を上げて高校受験に備えたい」という目標がある場合、すららの3教科コースは効果的な選択肢になるでしょう。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
すららの4教科コースは、主要3教科(国語・数学・英語)に加え、理科または社会を学習できるプランです。
理科や社会は暗記の要素が強い科目ですが、すららではAIを活用した復習システムや効率的な学習方法が取り入れられているため、短時間で効率よく知識を定着させることができます。
ここでは、すららの4教科コースの具体的な勉強効果について紹介します。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
理科や社会は、「一度学んだだけでは忘れてしまう」と感じることが多い科目です。
しかし、すららでは、要点を押さえた学習の後に、繰り返し復習できる仕組みが用意されています。
さらに、定期的に確認テストが実施されるため、どこが理解できていて、どこがまだ不十分なのかをAIが分析し、適切な復習を促してくれます。
これにより、知識がしっかりと定着し、テスト本番でもスムーズに解答できる力が身につきます。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
すららの理科・社会の学習は、ただ膨大な情報を詰め込むのではなく、重要なポイントをしっかり押さえて学べるように設計されています。
特に、暗記が苦手な子どもでも、イラストや図解を活用した解説があるため、イメージで理解しやすいのが特徴です。
「長時間勉強しているのに覚えられない…」という悩みを持つ子どもでも、短時間で効率よく知識を吸収できるので、時間対効果が非常に高い学習が可能です。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
学校の授業や通常の塾では、限られた時間内で多くの内容を学ぶため、どうしても「聞いて終わり」になりがちです。
しかし、すららなら、自分のペースで必要な部分だけを重点的に学習できるため、短時間で効率よくテスト対策ができます。
さらに、定期テスト対策用の問題演習も充実しているため、テスト本番でどのように解答すればよいのか、実践的なトレーニングができるのも強みです。
「テスト前に焦るのではなく、普段から計画的に学習したい」という方には、特におすすめの学習スタイルです。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
すららの5教科コースは、主要科目である国語・数学・英語に加え、理科・社会も学習できる総合型のコースです。
中学生にとって、内申点や高校受験に直結する5教科をバランスよく学ぶことは非常に重要です。
すららでは、AIを活用した弱点分析や効率的な学習計画によって、短時間でも効果的に学ぶことができます。
ここでは、すらら5教科コースの具体的な勉強効果について紹介します。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結 / 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
中学生にとって、内申点は高校受験に大きく影響します。
特に公立高校では、定期テストの成績や提出物などが評価され、5教科全体のバランスが求められます。
すららの5教科コースでは、すべての科目を均等に学習できるため、「得意科目だけ伸びる」「苦手科目が放置される」といった偏りを防ぐことができます。
AIが学習の進捗を管理し、苦手分野を重点的に復習できるため、内申点アップにもつながりやすいです。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ / 模試や過去問対策にも応用できる
高校受験では、単なる暗記ではなく、応用問題への対応力が求められます。
すららでは、基礎から応用へと段階的に学習できるカリキュラムが用意されており、受験対策にも適しています。
また、模試や過去問対策にも活用できるため、「普段の勉強+受験対策」として5教科コースを選ぶのもおすすめです。
苦手な単元をAIが自動で分析し、復習の必要な箇所をピックアップしてくれるため、効率的に受験準備が進められます。
勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
すららでは、5教科すべての学習状況をAIが管理し、最適な学習計画を提案してくれます。
「どこが苦手なのか」「どの単元を優先して学ぶべきか」を自分で考える必要がなく、すららのシステムに従って学習を進めるだけで効率よく知識を定着させることができます。
特に、「勉強のやり方がわからない」「どこを重点的に復習すればいいのかわからない」と悩んでいるお子さんにとって、最適なサポートとなるでしょう。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
すららの最大の強みは、「短時間でも学習効果が高い」と感じる人が多い点です。
学校の授業や一般的な塾では、一方的に説明を聞く時間が長くなりがちですが、すららでは「問題を解く→理解する→応用する」という流れがスムーズに進むため、無駄な時間がありません。
また、苦手分野にピンポイントで取り組めるため、効率的に成績を伸ばすことができます。
時間をかけずに効果的な学習をしたい方には、すららの5教科コースがぴったりです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
すららは、一般的な学習塾や学校の授業とは異なり、発達障害のあるお子さんや、不登校の子どもでも無理なく学べる仕組みが整っています。
「授業のスピードについていけない」「対人関係のストレスがある」といった悩みを持つ子どもたちにとって、すららの学習スタイルは大きな助けになります。
ここでは、すららが安心・安全に使える理由について詳しく紹介します。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
すららの最大の特徴のひとつは、学年に縛られず、自分のペースで学習できる「無学年式」の学習システムです。
学校の授業では「遅れをとるのが怖い」「みんなと同じペースで進まないといけない」といったプレッシャーがありますが、すららならそういったストレスから解放されます。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
すららでは、苦手な分野は過去の学年に戻ってじっくり学び直し、得意な分野はどんどん先へ進めることができます。
たとえば、小学生の子が中学英語を学んだり、中学2年生が小学校の算数を復習したりすることも可能です。
「学校の進度に合わせなければならない」という制約がないため、子ども一人ひとりの理解度に応じた学習ができ、無理なく続けられます。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
発達障害の特性に合わせた柔軟な学習スタイルが取れるのも、すららの大きなメリットです。
・ **ADHD(注意欠陥多動性障害)の子** → 集中力が続くタイミングで、一気に学習を進めることができる。
・ **ASD(自閉スペクトラム症)の子** → 毎日決まった時間・同じルーティンで学習することで、安心して学び続けられる。
それぞれの特性に応じた学習スタイルを選べるため、「無理なく続けられる」環境が整っています。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
学校や塾では、先生やクラスメートとの対人関係がストレスになることもあります。
すららでは、オンライン学習のため対面でのやりとりがなく、対人関係による緊張や不安を感じずに学ぶことができます。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
すららの授業は、アニメーションキャラクターによる対話型で進められます。
「間違えたから怒られる」「質問しづらい」といったことがなく、落ち着いた環境で学習が可能です。
また、キャラクターは感情的な反応をせず、常に穏やかに解説してくれるため、「間違えたらどうしよう」というプレッシャーを感じることなく、リラックスして取り組めます。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
不登校の子どもや、対人関係にストレスを感じやすい子どもにとって、「先生やクラスメートと話すのが苦手」「集団の授業だと質問しにくい」といった悩みがあります。
すららでは、そういったコミュニケーションのストレスを感じることなく、自分のペースで学べるのが大きなメリットです。
人と話すことに不安を感じる子どもでも、安心して学習を続けることができます。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは、発達障害を持つ子どもでもスムーズに学習できるように、「ユニバーサルデザイン」の考え方を取り入れています。
これは、「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように教材を設計することで、学習のハードルを下げ、無理なく続けられる環境を作るものです。
発達障害のある子どもはもちろん、学習に苦手意識を持っている子どもにとっても、使いやすいシステムとなっています。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
すららの教材は、子どもが学習につまずかないよう、分かりやすい構成になっています。
・ **イラストやアニメーションを活用** … 抽象的な概念も視覚的に理解しやすい。
・ **一つひとつの説明が丁寧** … 早いペースで進まないため、「置いていかれる」ことがない。
・ **学習の流れがシンプル** … 「何をすればいいのかわからない」と迷うことがない。
このような工夫があるため、発達障害の子どもでも安心して学習を進めることができます。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
読字障害(ディスレクシア)の子どもは、文章を読むのが苦手なことが多いですが、すららでは「音声での説明」があるため、文字を読むことに負担を感じることなく学習を進められます。
また、言語の理解に時間がかかるASD(自閉スペクトラム症)の子どもにとっても、アニメーションによる視覚的なサポートがあることで、内容をスムーズに理解しやすくなっています。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
発達障害のある子どもには、情報の処理方法に違いがあり、
・ **視覚優位の子** → 文字よりも映像やイラストを見たほうが理解しやすい。
・ **聴覚優位の子** → 読むよりも、音で聞いたほうが頭に入りやすい。
といった特徴があります。
すららでは、「アニメーション」「音声」「文字」の3つの要素を組み合わせた授業が行われるため、どちらのタイプの子どもにも適した学習方法を選ぶことが可能です。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
学習のペースは、子どもによって異なります。
「説明が速すぎると理解できない」「逆に、ゆっくりすぎると飽きてしまう」といったケースにも対応できるよう、すららでは音声速度を調整できる機能が搭載されています。
・ **ゆっくり聞きたい子** → 音声をスロー再生し、じっくり理解できる。
・ **早く進めたい子** → 再生速度を速めて、テンポよく学習を進められる。
このように、子どもの特性に合わせた柔軟な学習が可能なので、一人ひとりにとって最適なペースで学習できるのが、すららの大きな魅力です。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
すららは、間違えることを「学習の一部」として受け入れられるように設計されています。
学校や塾では、間違えたときに先生や周りの友達の目が気になり、「できない自分が恥ずかしい」と感じてしまう子どもも少なくありません。
しかし、すららでは、一人ひとりの学習ペースに合わせた設計になっており、間違えても否定されることなく、むしろ「どこが間違いだったのか」を納得しながら学び直せるようになっています。
これにより、子どもが安心して学習に取り組める環境が整っています。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららの学習システムでは、間違えたときに「これは違うよ」と否定されるのではなく、「どうしてこの答えになったのか」を考えさせる工夫がされています。
たとえば、問題を間違えた場合、すぐに正解を教えるのではなく、「ここをもう一度見直してみよう」と促す仕組みになっています。
このプロセスによって、「自分で考えて解決できた!」という成功体験を積み重ねることができ、自己肯定感を下げずに学習を続けられるのが特徴です。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
学校や塾では、「みんなの前で答えを間違えるのが怖い」「できない自分が情けない」と感じることがあるかもしれません。
特に、発達障害のある子どもは、「わからないことを聞くのが苦手」「間違えるとパニックになってしまう」といったケースもあります。
すららでは、一人で落ち着いて学習できる環境が整っており、誰かに見られる心配もないため、安心して問題に取り組むことができます。
「間違えても大丈夫」という安心感が、学習の継続につながるのが大きなメリットです。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
すららは、学習のモチベーションを維持しやすいように、「ゲーム感覚」で学べる工夫がされています。
一般的な学習教材は、「勉強=つまらない」と感じてしまうことが多いですが、すららではアニメキャラクターがナビゲートしてくれたり、クイズ形式で問題に挑戦できたりするため、「もっとやりたい!」という気持ちになりやすいのが特徴です。
特に、集中力が続きにくい子どもにとっては、「もう少しやってみよう」と思える仕組みがあることで、継続しやすくなります。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
すららでは、授業の進行をアニメキャラクターがサポートしてくれます。
親しみやすいキャラクターがナビゲートしてくれることで、学習が単調にならず、楽しみながら取り組めるのが特徴です。
また、クイズ形式で問題に挑戦できるため、ただの暗記ではなく「考えて答えを導き出す楽しさ」を感じられます。
「あと1問だけ」「もう少し進めてみよう」と、ゲームをプレイする感覚で学習が進むため、勉強に対する苦手意識を減らすことができます。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもは、即時フィードバックがあると学習のモチベーションを維持しやすいとされています。
すららでは、問題を解いた直後に「正解!」「いいね!」といった反応が返ってくるため、達成感を感じやすく、次の問題にも前向きに取り組みやすくなります。
また、短時間でも成果を感じやすい仕組みになっているため、「長時間集中するのが苦手」「興味が続かない」という子どもでも、楽しく学習を続けることができます。
すららの学習システムは、「勉強=つらいもの」ではなく、「楽しく続けられるもの」として設計されています。
ゲーム感覚で取り組める要素が多いため、勉強に対する抵抗感が少なく、自然と学習の習慣が身につくのが魅力です。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
発達障害のある子どもの学習をサポートするのは、親にとっても大きな負担になることがあります。
「どのように勉強を進めればいいのかわからない」「つまずいたときにどう対応すればいいのか不安」と感じることも少なくありません。
すららでは、専任の「すららコーチ」が学習の進め方をサポートしてくれるため、親がすべてを抱え込む必要がなく、安心して見守ることができます。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
すららコーチは、学習指導の専門知識を持っているだけでなく、発達障害の特性を理解した対応ができるのが特徴です。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもには、「短時間で達成感を得られる学習スタイル」を提案したり、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもには、「学習の流れを予測しやすい環境」を整えてあげるなど、一人ひとりに合ったサポートをしてくれます。
また、学習障害(LD)のある子どもには、読み書きの負担を軽減しながら理解を深められる方法をアドバイスするなど、個別のニーズに合わせた対応が可能です。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
すららでは、子ども一人ひとりの特性やペースに合わせた学習計画を、すららコーチが作成してくれます。
「今日は何を勉強すればいいのか」「どの単元が苦手なのか」が明確になるため、親が細かくスケジュールを管理する必要がありません。
また、つまずいたポイントをAIが分析し、すららコーチが具体的なアドバイスをしてくれるため、「どこが理解できていないのか」を親が細かくチェックしなくても、適切なフォローが受けられます。
このように、親の負担を軽減しながら、子どもが自信を持って学習を続けられる環境が整っています。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
すららは、タブレットやパソコンがあれば、自宅で学習を完結できる完全オンライン型の学習教材です。
発達障害のある子どもや、不登校の子どもにとっては、通学や対面授業のストレスが大きな負担になることがありますが、すららならそうした心配がなく、安心して学習を続けられます。
また、親にとっても「送迎の負担がない」「決まった時間に学習を開始できる」といったメリットがあり、学習環境を整えやすいのが特徴です。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
すららは、特別な機材を用意する必要がなく、タブレットやパソコン1台があればすぐに学習を始めることができます。
塾や家庭教師のように移動の手間がないため、子どもが「今すぐ勉強したい」と思ったときにすぐ取り組めるのがメリットです。
また、親も「送り迎えをしなくていい」「学習の様子をすぐに確認できる」といった点で負担が少なく、日々の生活の中に無理なく学習を組み込むことができます。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
不登校の子どもや、発達障害の特性で学校の授業についていくのが難しい子どもにとって、一番の不安は「学習の遅れ」です。
すららでは、無学年式の学習システムを採用しているため、学校の進度に縛られることなく、自分のペースで学ぶことができます。
「授業についていけないから勉強が嫌になる」「勉強ができないから自己肯定感が下がる」といった悪循環を防ぎ、少しずつでも学習を進めることで、子どもが自信を持てるようになります。
すららの「完全オンライン学習」は、学習の負担を減らしながら、無理なく続けられる環境を提供します。
親のサポートが必要な部分もすららコーチがフォローしてくれるため、親子でストレスを抱え込むことなく、安心して学習を続けられるのが大きな魅力です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
すららは、自宅で学習できる便利なタブレット教材ですが、利用をやめたい場合には解約や退会の手続きをする必要があります。
ただし、「解約」と「退会」はそれぞれ意味が異なり、手続きの内容も違うため、事前に理解しておくことが大切です。
ここでは、すららの解約・退会の違いや、具体的な手続き方法について詳しく紹介します。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
すららをやめる際に気をつけたいのが、「解約」と「退会」の違いです。
どちらも「利用をやめる」手続きですが、それぞれの意味が異なります。
すららの解約は「利用を停止すること」。毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
「解約」は、すららの利用を停止し、月額料金の支払いをストップする手続きです。
解約をしても、すぐに会員情報が消えるわけではなく、一定期間データが保持されることが多いです。
将来的に再開する可能性がある場合は、解約手続きを行うことで、一時的に利用を中止することができます。
すららの退会は「すららの会員そのものをやめること」。データも消える。
「退会」は、すららの会員情報そのものを削除する手続きです。
退会すると、学習履歴や設定した学習計画などのデータが消えてしまうため、後から再開したくても以前のデータを復元することはできません。
「今後すららを使う予定がない」「完全に利用をやめたい」という場合は退会手続きを行いますが、再開する可能性がある場合は「解約」にとどめておくほうがよいでしょう。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららの解約をするには、専用のサポートセンター「すららコール」に電話をする必要があります。
メールやWEB上では解約手続きを受け付けていないため、必ず電話で手続きを行う必要があります。
| 【すららコール】 0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
すららの解約は、電話での手続きが必要であり、メールや公式サイトのマイページから解約することはできません。
そのため、「解約をしたい」と思ったら、営業時間内にすららコールへ電話をかける必要があります。
特に、月末ギリギリに解約しようとすると、電話が混み合ってつながりにくくなる可能性があるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
解約の手続きを進める際には、本人確認が必要になります。
電話をかける際に、登録者の氏名やID、契約時の電話番号などを求められるため、事前に準備しておくとスムーズに進めることができます。
特に、契約者が保護者の場合は、子どもの情報と契約者の情報を間違えないように注意が必要です。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
解約の際には、「いつまで利用したいか」を伝える必要があります。
ただし、すららの解約では**日割り計算は行われず、解約を申し出た月の末日までの利用料金が発生**します。
そのため、月の途中で解約しても、その月の料金は支払う必要があることを理解しておきましょう。
できるだけ損をしないようにするためには、月末ギリギリではなく、余裕をもって解約手続きを進めることがポイントです。
すららの解約・退会は、電話での手続きが必要であり、日割り計算が適用されない点など、事前に知っておくべきルールがあります。
利用をやめる場合は、事前に確認し、スムーズに手続きを進められるように準備しておくことが大切です。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
すららを完全にやめたい場合は、「解約」だけでなく「退会」手続きも必要になります。
解約をすると、利用料金の支払いは停止されますが、すららの会員情報や学習データはそのまま残ります。
一方、退会をすると、すららの会員情報そのものが削除され、学習履歴や設定した学習計画などのデータも消えてしまいます。
そのため、「今後すららを使う予定がない」「個人情報を完全に削除したい」という場合は、解約後に退会手続きを行うことをおすすめします。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
退会を希望する場合は、解約の電話をする際に「退会も希望している」と伝えると、解約と同時に退会手続きも進めてもらうことができます。
ただし、解約手続きが完了するまでは退会処理は行われないため、必ず先に解約の手続きを済ませる必要があります。
また、退会をすると、学習履歴やアカウント情報が完全に削除されるため、再度すららを利用したくなった場合でも、以前のデータを引き継ぐことはできません。
「また利用するかもしれない」という場合は、退会せずに解約のみにしておくと良いでしょう。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
すららの解約後、退会をしなくても特に問題はなく、料金の支払いは停止されます。
そのため、「データを残しておきたい」「また利用する可能性がある」という場合は、退会をせずに解約のみを行うのがよい選択となります。
退会をしてしまうと、学習履歴や進捗データが削除されてしまい、再開した際にゼロからのスタートになってしまいます。
特に、過去の学習データを参考にしたい場合は、退会せずにアカウントを残しておくほうが安心です。
すららを解約する際は、退会するかどうかを慎重に判断し、自分にとって最適な方法を選ぶようにしましょう。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
すららは、無学年式で自由に学べるタブレット教材ですが、「どうやって使うのが一番効果的なの?」と悩む方もいるかもしれません。
特に小学生は、学習の習慣を身につけることが大切なので、効果的な使い方を工夫することで、学習の定着率が大きく変わってきます。
ここでは、小学生向けにすららを活用する際のコツを紹介していきます。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生のうちは、長時間の勉強が難しいことも多く、「飽きずに続けること」が大きなポイントになります。
また、すららの強みを活かして、楽しく学習できる工夫をすることで、無理なく学習習慣を定着させることができます。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
小学生は集中力が続きにくいため、「1回の学習時間を短めに設定すること」がポイントです。
すららでは、短いユニットごとに区切られているため、1回20〜30分程度を目安に、毎日少しずつ進めるのがおすすめです。
「今日は1ユニットだけ」「計算問題だけ」など、小さな目標を立てることで、学習のハードルを下げることができます。
学習時間が長すぎると「勉強が嫌だ」という気持ちが強くなってしまうので、無理のない範囲でコツコツ続けることが大切です。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
小学生は、目に見える「ごほうび」があるとやる気が続きやすい傾向があります。
そのため、1ユニット終わったら「シールを貼る」「スタンプを押す」といった簡単なごほうびを用意すると、楽しく学習を続けられます。
すららには、学習の進捗がわかる機能もあるので、「何回勉強したら○○がもらえる」という目標を設定すると、モチベーションを維持しやすくなります。
達成感を感じられる工夫を取り入れることで、勉強に対するポジティブな気持ちを育てることができます。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
低学年のうちは、「勉強=楽しいもの」と感じられるかどうかが、学習習慣を身につけるカギになります。
そのため、親が「勉強しなさい!」と指示するのではなく、「一緒にやろう!」と声をかけることで、子どもが前向きに取り組みやすくなります。
すららのアニメーション授業は、親が見てもわかりやすく、親子で一緒に学習するのにも適しています。
特に最初のうちは、親がそばについて「どんなふうに進めるのか」を見守ることで、安心して取り組めるようになります。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/ 好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
すららは、AIが学習データを分析し、苦手な部分をピンポイントで指摘してくれる機能があります。
そのため、最初にAI診断を活用し、苦手な部分を把握することから始めるのがおすすめです。
小学生は好きな科目だけをやりがちですが、それでは学習に偏りが出てしまいます。
苦手な単元を克服しながら進めることで、全体の学力バランスを整えることができます。
特に、算数や国語の基礎がしっかりしていないと、学年が上がるにつれてつまずきやすくなるため、小学生のうちに苦手をなくしておくことが重要です。
すららは、子どもが楽しく続けられるように工夫されている教材ですが、使い方次第で学習の効果が大きく変わります。
無理なく毎日続ける工夫をしながら、学習習慣をしっかり身につけていきましょう。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、定期テストや高校受験を意識した学習が必要になります。
小学生の頃と違い、学習量が増え、部活や習い事と両立しながら勉強を進めなければならないため、効率よく学ぶことが重要です。
すららは、定期テスト対策や苦手克服に役立つ機能が充実しているため、正しく活用することで効果的に学習を進めることができます。
ここでは、中学生向けのすららの効果的な使い方を紹介します。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
中学生にとって、定期テストは内申点に大きく関わるため、計画的な学習が必要になります。
すららでは、各単元ごとに「まとめテスト」が用意されているため、テスト範囲に合わせて学習を進めることで、効率よく得点力をアップできます。
具体的には、テストの日程を確認したうえで、「今どの範囲を勉強するべきか」を逆算しながら進めるのがおすすめです。
学校の授業より少し先を予習しながら進めることで、授業内容の理解も深まり、テスト直前には復習に集中できるようになります。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
中学生は部活や習い事などで忙しく、なかなか勉強の時間を確保できないことがあります。
そこでおすすめなのが、「寝る前のタブレット学習ルーティン」を決めることです。
すららは、スマホやタブレットがあればどこでも学習できるため、夜の10~20分程度を学習時間として固定すると、無理なく勉強を習慣化できます。
特に、英単語や数学の計算問題などは、寝る前に学習すると記憶に定着しやすいため、短時間でも効果的に学習を進めることができます。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
すららには、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートサービスがあり、学習計画のアドバイスやつまずきのフォローをしてくれます。
中学生になると、勉強の難易度が上がるため、「どこが苦手なのか」「どのように勉強を進めればよいのか」がわからなくなることもあります。
すららコーチを活用することで、学習の進め方に迷うことなく、最適な方法で勉強を進められるようになります。
また、「なかなかやる気が出ない」という場合にも、コーチがモチベーションを上げるアドバイスをしてくれるため、学習を継続しやすくなります。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
中学生の学習では、「復習」と「予習」のバランスを取ることが大切です。
すららでは、無学年式の学習ができるため、復習として前の学年の内容に戻ることも、予習として先の学年の内容を学ぶことも可能です。
特に、英語や数学は予習をすることで授業の理解度が大きく変わるため、事前に学習しておくと、学校の授業がスムーズに進みます。
一方で、苦手な分野は復習をしながら基礎を固めることで、確実に実力を伸ばすことができます。
すららは、中学生が効率よく学習を進められるように設計された教材です。
定期テスト対策や学習習慣の定着、苦手克服など、目的に応じて活用することで、より効果的に学習を進めることができます。
自分に合った学習方法を見つけ、継続的に取り組むことが大切です。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると、学習内容が一気に高度になり、定期テストだけでなく、模試や共通テストなど、将来を見据えた勉強が求められます。
また、「苦手科目を克服しないと成績が伸びない」「授業のペースについていけない」「勉強のモチベーションが続かない」など、学習に関する悩みも増えてきます。
すららを上手に活用することで、自分のペースで効率よく学習を進めることができます。
ここでは、高校生向けのすららの効果的な使い方を紹介します。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校の勉強は、基礎がしっかりしていないと応用問題に取り組むのが難しくなります。
すららでは、無学年式の学習システムを活用し、つまずいた部分まで戻って復習することが可能です。
例えば、「数学の微分が苦手なら、中学の関数の基礎から復習する」「英語の長文読解が苦手なら、中学レベルの文法を振り返る」といった学習ができます。
一方で、得意科目は発展問題に挑戦し、得点力をさらに伸ばすことができます。
「苦手の克服」と「得意の強化」をバランスよく進めることで、安定した学力を身につけることができます。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
高校の授業は、クラス全員の進度に合わせて進むため、「授業が速すぎてついていけない」「逆に簡単すぎて物足りない」と感じることがあります。
すららを活用すれば、自分の理解度に合わせたペースで学習を進められるため、「授業についていけない」「もっと先取りしたい」といった悩みを解決できます。
特に、理系科目は積み重ねが重要なので、授業の進度に関係なく、自分の理解度に応じた学習を進めることが大切です。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
高校生の学習では、模試や共通テストに向けた対策が重要になります。
すららは、特に基礎力の定着に強みがあるため、模試や共通テストの基礎固めとして活用できます。
例えば、「模試で苦手な単元が分かったら、すららで復習する」「共通テストの出題範囲をすららで網羅的に学習する」といった使い方が可能です。
特に、英語のリスニングや数学の基礎計算などは、繰り返し学習することで確実に得点力を向上させることができます。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
高校生になると、学習計画を立てて、どれだけ勉強できたかを把握することが重要になります。
すららでは、学習時間や達成度をグラフで可視化できるため、「今日は何時間勉強したか」「どの単元を重点的に学習したか」を一目で確認できます。
これにより、勉強のモチベーションを維持しやすくなり、学習の進捗管理がしやすくなります。
また、目標を設定しやすくなるため、「1週間でこの単元を終わらせる」「模試前にこの分野を重点的に学習する」といった計画的な学習が可能になります。
高校生がすららを効果的に活用するには、「苦手克服と得意強化を並行する」「授業の進度に合わせず、自分のペースで学ぶ」「模試や共通テスト対策に活用する」「学習時間を可視化して進捗管理する」といったポイントを意識することが大切です。
すららを上手に活用し、効率よく学習を進めていきましょう。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校の子どもにとって、学習を続けることはもちろんのこと、生活リズムを整えたり、自信を回復したりすることが大切です。
しかし、「何から始めたらいいかわからない」「学校の授業に追いつけるか不安」と感じることも多いでしょう。
すららは、不登校の子どもでも無理なく学習を進められるように設計されており、学力面だけでなく、精神面のサポートにもつながる工夫がされています。
ここでは、不登校の子どもがすららを効果的に活用する方法を紹介します。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校になると、学校に通わないことで生活リズムが崩れやすくなります。
夜更かしが増えたり、昼夜逆転してしまったりすると、勉強に取り組む気力もなくなってしまうことがあります。
そこで、すららを活用して「ミニ時間割」を作ることで、生活リズムを整えることができます。
例えば、「朝9時に起きる→10時から30分だけ学習→休憩→午後にもう30分」といったように、小さなスケジュールを立てることで、少しずつ規則正しい生活を取り戻すことができます。
すららは、自分のペースで学べるため、無理なく「決まった時間に学習する習慣」を作ることができるのが特徴です。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
不登校の子どもにとって、「周囲の目を気にせず、自分のペースで学習できる環境」はとても重要です。
学校の授業では、クラスメイトと一緒に勉強しなければならないため、「わからないことを質問しづらい」「授業のペースについていけない」といったプレッシャーを感じることがあります。
しかし、すららなら、すべての学習を自宅で完結できるため、安心して学習を進めることができます。
また、すららは対話型アニメーション授業を採用しているため、「一人で勉強している感覚が少ない」のも特徴です。
アニメキャラクターがナビゲートしてくれることで、「誰かと一緒に学んでいる」という感覚が生まれ、学習への抵抗感を減らすことができます。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
不登校の子どもは、「自信を失っている」ことが多いため、学習を通じて少しずつ成功体験を積み重ねることが重要です。
すららには、「ほめ機能」が搭載されており、問題を正解するたびにアニメキャラクターが褒めてくれる仕組みになっています。
「よくできたね!」「すごい!」といったポジティブな言葉をかけてもらうことで、「できた!」という達成感を味わいやすくなります。
また、「1つのユニットをクリアしたら、お気に入りのおやつを食べる」「1週間続けたら、好きなゲームを30分やってOK」など、小さなごほうびを設定することで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。
無理に長時間勉強するのではなく、「できたことをしっかり認めてあげる」ことが、不登校の子どもが学習を続けるコツです。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校の子どもにとって、「誰かに相談できる環境」があるかどうかは非常に重要です。
すららには、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの専門スタッフがいて、学習計画のアドバイスやモチベーション管理をサポートしてくれます。
親が「勉強しなさい」と言うと、子どもはプレッシャーを感じてしまうことがあります。
しかし、すららコーチのような第三者がアドバイスをすると、「先生じゃないけど、頼れる大人」という存在になり、子どもも素直に話を聞きやすくなります。
また、「どうやって勉強を進めればいいかわからない」という悩みにも、具体的な学習計画を立ててくれるため、安心して学習を続けることができます。
不登校の子どもがすららを活用する際は、「生活リズムを整える」「一人でも安心して学べる環境を作る」「成功体験を増やして自信を回復する」「すららコーチを活用して孤立感を減らす」といったポイントを意識することで、より効果的に学習を進めることができます。
焦らず、自分のペースで無理なく取り組むことが大切です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照: 会社概要 (すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららはうざいという口コミがある原因について考察してみましょう。
この口コミが生まれる理由にはいくつかの要因が挙げられます。
まず第一に、個人の感性や価値観の違いが関与している可能性があります。
人々は異なる偏見や好みを持っており、そのため、すららの特性が一部の方々には違和感を与えているのかもしれません。
また、コミュニケーションの取り方においても、意図や伝わり方に誤解が生じることがあるかもしれません。
さらに、利用者個人の過去の経験や背景によっても、すららを「うざい」と感じる要素が生まれる可能性が考えられます。
一方で、すららがうざいと感じられる理由は、コンテンツや機能の過剰なプッシュ、広告の多さ、情報過多などが考えられます。
ユーザーが求める情報や体験とのバランスが崩れていると、使いにくさやストレスを感じる傾向が出てくることもあります。
したがって、すららがうざいと感じる口コミについては、その要因を客観的に分析し、改善点を明確にすることが重要です。
利用者の声に耳を傾け、適切な対応を取ることで、より使いやすいサービスへと進化させることができるでしょう。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
当社の発達障害コースでは、お子様の状況やニーズに合わせて様々な料金プランをご用意しております。
発達障害に関する支援は、個々のお子様に合わせたオーダーメイドのアプローチが重要であり、そのために柔軟性のある料金設定を心がけております。
例えば、週に何回コースを受講するかや、サポートの内容によって料金が異なります。
また、長期的なプランや短期的なプランなど、お子様の状況に最適なプランをご提案いたします。
料金プランに関する詳細やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
皆様のお子様がより良いサポートを受けられるよう、尽力してまいります。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
不登校の子供たちの教育への関心が高まる中、すららのタブレット学習が注目を集めています。
保護者の皆様からは、「すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?」といった疑問が多く寄せられています。
不登校の子供に対する教育の在り方は重要ですが、すららのタブレット学習はあくまで補完的な教材であり、学校への出席扱いにはなりません。
重要な点としては、すららのタブレット学習は個人の自己学習をサポートするツールであり、学校通学とは異なるものです。
従って、不登校の子供たちにとって、すららのタブレット学習が出席扱いになることはありません。
学校への登校を代替するものではなく、学習の補完として位置付けられます。
不登校の子供たちに教育の機会を提供するためには、教育機関との連携や個別のサポートが必要です。
保護者の皆様におかれましては、すららのタブレット学習を利用する際には、教育機関との協力や指導教材としての活用を検討することが重要です。
不登校の子供たちに適切な教育環境を提供するためには、専門家との相談や教育委員会との連絡など、緊密な連携が不可欠です。
すららのタブレット学習は教育の手段として有用ですが、出席扱いにはならないことを理解しておくことが大切です。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードの使い方についてご質問いただき、ありがとうございます。
当記事では、すららのウェブサイトやアプリにおいてキャンペーンコードを使う方法について詳しく説明いたします。
まず、すららのキャンペーンコードをご利用いただく際には、通常は商品購入時に入力することが一般的です。
商品を選択し、お支払い画面に進む際に、「キャンペーンコードを入力する」という欄がございますので、そちらに該当のコードをご入力ください。
キャンペーンコードを正しく入力いただいた後には、自動的に割引や特典が適用されます。
画面上に明記されている金額が変更されるか、特典が表示されるかをご確認いただくことで、正しくキャンペーンコードが利用されているかどうかが確認できます。
また、ご不明点やキャンペーンコードの入力方法に関する疑問がございましたら、すららのカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
丁寧に対応させていただきます。
使い方についてのご質問はお気軽にどうぞ。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
弊社のオンラインサービス「すらら」を利用していただき、誠にありがとうございます。
退会手続きに関する詳細についてご案内いたします。
退会手続きは以下のステップに従って行うことができます。
まず、ログイン後に画面右上にある「マイページ」をクリックしてください。
次に、「アカウント設定」をクリックし、その中から「退会手続き」を選択してください。
その後、画面に従って必要事項を入力し、手続きを完了させてください。
退会手続き完了後は、ご登録いただいた情報が全て削除されますので、予めご了承ください。
また、退会手続き完了後に再度アカウントを復活させることはできませんので、ご注意ください。
何かご不明点がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでお問い合わせください。
ますます便利で使いやすい「すらら」をご提供できるよう努めてまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららを利用する際に必要な料金は、基本的に「入会金」と「毎月の受講料」のみです。
追加教材の購入が必須ではなく、オンライン上で完結する学習システムのため、紙の教材や問題集を別途購入する必要はありません。
ただし、学習を進めるためには、インターネット環境とタブレットまたはPCが必要となるため、それらの設備を準備する必要があります。
また、一部の支払い方法(クレジットカード以外)では手数料が発生する場合があるため、契約時に詳細を確認するのがおすすめです。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは、**1つの契約で兄弟・姉妹と一緒に利用することが可能**です。
例えば、小学生と中学生の兄弟がいる場合、1つのアカウントを共有し、それぞれの学年に合わせた学習を進めることができます。
ただし、学習の進捗データは1つのアカウント内で管理されるため、兄弟それぞれの進捗を個別に記録したい場合は、別々のアカウントを契約する必要があります。
1契約で複数人が利用できる点は、特に兄弟で学習を進めたい家庭にとって、コスト面でもメリットが大きいです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには、**英語の学習プログラムも含まれています**。
英語の学習内容は、「リスニング」「スピーキング」「リーディング」の3技能をバランスよく学べる構成になっており、ネイティブの発音を聞きながら学べるのが特徴です。
また、アニメーションを使った対話型授業が取り入れられているため、楽しく英語を学ぶことができます。
小学校で必修化された英語学習に対応し、基礎からしっかり学べるカリキュラムになっているので、英検対策としても活用できます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららには、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートスタッフが在籍しており、**個々の学習状況に合わせたアドバイスを受けることができます**。
具体的なサポート内容としては、以下のようなものがあります。
1. **学習計画の作成・アドバイス**
学習の進め方がわからない場合、すららコーチが「どの単元を優先して学習すべきか」「どのようなペースで進めるとよいか」などを提案してくれます。
2. **つまずきポイントの分析・対策サポート**
すららにはAIがつまずきを分析する機能がありますが、すららコーチは、さらに詳しく「なぜ理解できないのか」「どのような学習方法を取るとよいか」といった具体的な対策を提案してくれます。
3. **学習のモチベーション維持サポート**
学習が長続きしない、やる気が出ないといった悩みに対して、コーチが適切な声かけをしてくれます。
親以外の第三者がサポートすることで、子どもが素直にアドバイスを受け入れやすくなります。
4. **保護者向けの学習状況報告**
子どもの学習状況について、保護者にレポートが送られるため、進捗を把握しやすくなっています。
学習習慣が定着しているか、どの科目が苦手かなどを把握するのに役立ちます。
すららコーチのサポートを活用することで、学習の進め方に悩むことなく、効率よく学習を進めることができます。
特に、不登校や発達障害のある子どもにとっては、**親以外の相談相手がいることで、学習のモチベーションを維持しやすくなる**のが大きなメリットです。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
【すらら】に関する口コミや料金、最悪の噂についてまとめました。
この記事を通じて、【すらら】を検討されている方々がより情報を得る手助けとなれば幸いです。
口コミや評判には個人の主観が含まれるため、さまざまな意見を参考にしながら自身に合った判断をされることが大切です。
また、料金面についても慎重に比較検討し、ご家庭やお子様に最適なプランを選択されることをお勧めします。
【すらら】を利用する際には、お子様の学習スタイルや目的に合った教材を選ぶことが重要です。
さまざまな教材やコンテンツが揃っているため、お子様が興味を持ちやすいものを選んで学習意欲を高めることがポイントです。
また、学習環境や進捗管理など、保護者の方々もサポート体制を整えることで、お子様の学習効果を最大限に引き出すことができるでしょう。
最後に、【すらら】を活用することで、お子様の学習をより効果的にサポートすることができる可能性があります。
しかし、教材選びや利用方法には慎重さが求められます。
お子様の成長と学習を真剣に考え、適切なサポートを提供していくことが大切です。
【すらら】を通じて、お子様の学び舎をより豊かなものにしていく手助けとなることを願っています。

